お急ぎの方はコチラ
受付時間:平日9:00 - 18:00
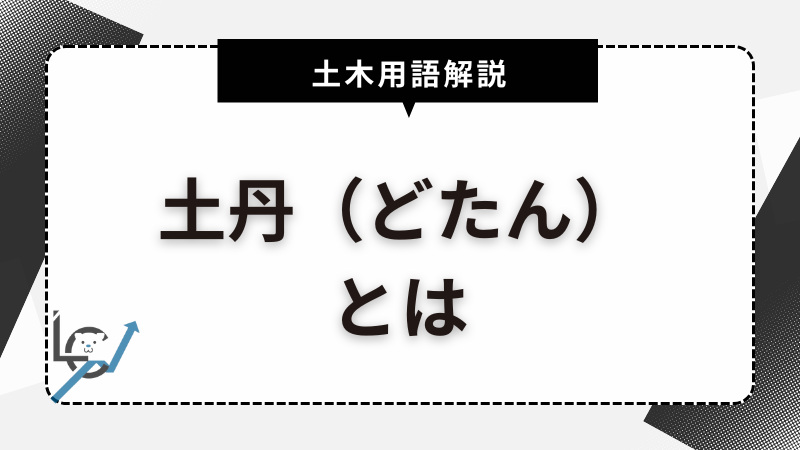

土丹(どたん)とは、関東地方の地下に広く分布する固結した粘土層のことです。青灰色から黒灰色の色調を持ち、非常に硬く締まっています。乾燥すると固結度が増し、湿潤状態では軟化する性質があります。
建設業界では、土丹層は地盤の安定性に関わる重要な要素です。土木工事では通常の土とは異なる掘削方法や対策が必要となるため、事前の地盤調査が重要になります。
「土丹岩」とも呼ばれ、主に関東平野の地下、特に東京湾岸地域や武蔵野台地の下層部分に多く分布しています。
土丹(どたん)は地質学的には第三紀層または第四紀層に属する堆積岩の一種です。形成年代は約100万年前から300万年前とされています。海底に堆積した粘土が長い年月をかけて圧縮・固結し、現在の状態になりました。
土丹の物理的特性として、含水比が低く、圧縮強度が高いことが挙げられます。N値(地盤の硬さを示す指標)は30〜50程度と非常に高い値を示すことが多いです。このため、一般的な掘削機械では容易に掘り進めることができない場合があります。
土丹層の厚さは場所によって異なりますが、数メートルから数十メートルに及ぶこともあります。層の上部は風化作用により若干軟らかくなっていることが多いですが、深部に行くほど硬質になる傾向があります。
また、土丹には微細な亀裂が入っていることがあり、この亀裂に沿って地下水が流れることがあります。そのため、掘削時に予期せぬ湧水が発生することもあるため注意が必要です。
地域によっては土丹層の上に軟弱な沖積層が堆積していることがあり、この場合は地盤としての評価が複雑になります。建築や土木の計画においては、土丹層の分布状況を正確に把握することが不可欠です。
土丹(どたん)を掘削する際には、以下の5つの重要な注意点があります。
土丹は非常に硬いため、一般的な掘削機械では対応できないことがあります。硬質地盤に適した掘削機械を選定することが必要です。
掘削中に土丹が乾燥すると、さらに硬化して作業効率が低下します。常に適切な湿潤状態を保つための散水などの対策が重要になります。
土丹層には亀裂が存在することがあり、その亀裂から突然の湧水が発生する可能性があります。事前の地盤調査で地下水の状況を把握し、排水設備を準備しておくことが必要です。
掘削によって応力状態が変化し、周辺地盤の沈下や変形を引き起こす可能性があります。適切な土留め工法の選定と施工が重要です。
掘削後の土丹は空気に触れることで風化が進み、物性が変化します。特に雨水の影響を受けると急速に強度が低下することがあるため、掘削面の保護対策も必要となります。
【お役立ち情報】
コメント