お急ぎの方はコチラ
受付時間:平日9:00 - 18:00
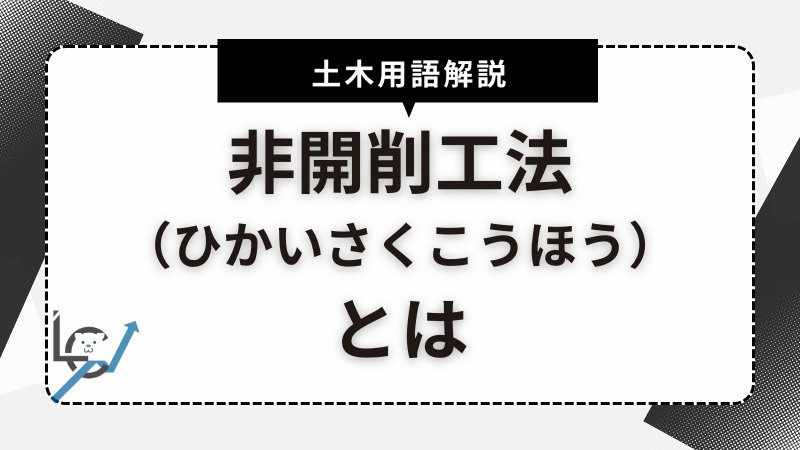
非開削工法(ひかいさくこうほう)とは、地上を掘り返さずに地下に管路やトンネルを構築する工法です。
この工法は、地表面への影響を最小限に抑えながら地下インフラを整備できる点が最大の特徴です。主に都市部での上下水道管の敷設や通信ケーブルの埋設、小規模なトンネル建設などに利用されています。
非開削工法には主に「推進工法」と「シールド工法」の2種類があり、工事の規模や目的に応じて使い分けられています。交通量の多い道路下や河川横断部など、地上での工事が困難な場所で特に重要な役割を果たしています。
近年では技術の進歩により適用範囲が広がり、環境への配慮や工期短縮の観点からも、非開削工法の需要は今後さらに高まると予想されています。
非開削工法(ひかいさくこうほう)には様々な種類があります。ここでは代表的な工法について詳しく説明します。
推進工法は、発進立坑から到達立坑へ向けて管を押し込む方式の非開削工法です。
この工法では、発進立坑側に設置した油圧ジャッキなどの推進装置によって管を地中に押し込みます。管の先端部には掘削刃を備えた掘進機を取り付け、地盤を掘削しながら管を前進させていきます。
推進工法は主に小口径から中口径(直径800mm〜3000mm程度)の管を埋設する際に用いられ、100m前後の比較的短い距離の工事に適しています。上下水道管や雨水幹線などの敷設に広く利用されています。
地盤条件や施工深度によって、泥水式や土圧式など異なる推進方式が選択されます。
シールド工法は、シールドマシンと呼ばれる円筒形の掘削機を使用する非開削工法です。
掘削機の前面にあるカッターヘッドで地盤を掘り進めながら、後方ではプレキャストコンクリート製のセグメントを組み立てて覆工(トンネルの内側の構造物)を構築していきます。
シールド工法は主に大口径(直径3000mm以上)のトンネルや長距離の管路構築に適しており、地下鉄や道路トンネル、大規模な下水道幹線などに活用されています。
地盤条件に応じて、泥水式シールド、土圧式シールド、開放型シールドなど様々な種類があります。
小口径管推進工法は、直径800mm未満の小口径管を埋設するための非開削工法です。
この工法は推進工法の一種で、小型の掘削機を使用するため、狭い場所での施工も可能です。無人で遠隔操作により施工するため、作業の安全性が高いという特徴があります。
主にガス管や水道管など、比較的小さい管路の埋設に用いられています。
その他にも様々な非開削工法があります。「パイプルーフ工法」は複数の鋼管を地中に打ち込んで傘のような構造を作り、その下を掘削する方法です。「アンダーピニング工法」は既存構造物の下を非開削で補強する技術です。
また「HDD工法(水平方向掘削工法)」は、地表から斜めに掘り進め、所定の深度に達した後水平方向に掘削し、管を引き込む方法で、河川や道路を横断する管路敷設などに用いられます。
開削工法と非開削工法(ひかいさくこうほう)には、施工方法や環境影響において明確な違いがあります。
以下の表は、両工法の基本的な違いを示しています。
| 比較項目 | 開削工法 | 非開削工法 |
|---|---|---|
| 施工方法 | 地表から掘削して埋設 | 地表をほとんど掘らずに地下で施工 |
| 交通影響 | 大きい(交通規制が必要) | 小さい(最小限の規制) |
| 騒音・振動 | 大きい | 比較的小さい |
| 適用範囲 | 浅い深度の工事 | 様々な深度の工事に対応可能 |
開削工法は地表から直接掘削するため、工事範囲が広く交通規制の影響が大きくなります。また、大型重機を使用するため騒音・振動も発生しやすいです。
一方、非開削工法は立坑と呼ばれる作業用の縦穴を数か所設置するだけで済むため、地上への影響が最小限です。地下での作業が中心となるため、周辺環境への負荷も抑えられます。
工事の規模や場所、周辺環境などを考慮して、両工法のうちどちらが適しているかを判断することが重要です。
承知しました。h2の本文を例示されたスタイルに合わせて修正します。
非開削工法(ひかいさくこうほう)のメリットには主に5つあります。
それぞれ説明していきましょう。
非開削工法の最大のメリットは、交通への影響を最小限に抑えられる点です。
従来の開削工法では工事区間全体を掘り返すため、大規模な交通規制が必要でした。一方、非開削工法では発進立坑と到達立坑という限られた場所だけを掘削するため、交通規制の範囲が大幅に縮小されます。
特に交通量の多い幹線道路や繁華街、鉄道の下を横断する工事では、この利点が大きく活かされます。渋滞緩和や迂回路設置の最小化により、社会的コストの削減にも貢献しています。
非開削工法は環境に優しい工法としても評価されています。
掘削量が大幅に減少するため、建設残土の発生量が少なく、その処理・運搬に関わる環境負荷も低減されます。また工期短縮により重機の稼働時間も削減され、二酸化炭素排出量の抑制につながります。
騒音や振動、粉塵の発生も抑えられるため、周辺住民や生態系への影響も最小限に抑えることができます。環境規制が厳しくなる現代において、この環境面での利点は重要な意味を持っています。
非開削工法では地下で作業を行うため、地上の構造物や設備への影響を最小限に抑えられます。
掘削範囲が限定されるため、電柱、街路樹、ガス管、水道管などの既存設備への影響が少なく、移設や防護の必要性が減少します。特に歴史的建造物や重要インフラが密集する地域での工事に適しています。
地盤沈下や周辺建物への影響も少ないため、工事によるトラブルやクレームも減少し、スムーズな工事進行が期待できます。
非開削工法は多くの場合、従来の開削工法と比較して工期の短縮が可能です。
地表面の復旧作業が最小限で済むため、全体の工期を短縮できます。また天候の影響も受けにくいため、計画通りに工事を進めやすいという利点もあります。
工期短縮は交通規制期間の短縮にもつながり、社会的な影響を最小限に抑えるとともに、早期のインフラ供用開始による経済的メリットも見込めます。
非開削工法は様々な条件下での施工に対応できる柔軟性を持っています。
深い位置への埋設や、河川・鉄道などの障害物を横断する工事でも対応可能です。地下水位の高い場所や軟弱地盤でも安定した施工ができ、近年では曲線施工や急勾配施工も可能になってきています。
この柔軟性は都市部の複雑な地下空間でのインフラ整備において特に重要で、他の地下構造物との干渉を避けながら施工できる大きな利点となっています。
非開削工法(ひかいさくこうほう)にはメリットだけでなく、いくつかのデメリットも存在します。
それぞれ説明していきましょう。
非開削工法の最も大きなデメリットは、初期投資コストが高額になりやすい点です。
シールドマシンや推進機などの専用機械は高価であり、立坑の構築にも費用がかかります。特に小規模な工事では、この初期コストが全体の工事費に占める割合が大きくなります。
開削工法と比較すると、短い距離の工事では非開削工法のほうがコスト高になるケースが多いです。ただし、交通規制による社会的コストも含めた総合評価では、非開削工法が優位になることもあります。
非開削工法は高度な技術と専門知識を必要とする工法です。
施工管理や機械操作に専門的な技術が求められ、地盤状態を正確に把握して適切な掘進管理を行う必要があります。これらの技術を持つ人材の確保が課題となります。
専門業者が限られているため、工事の発注先が限定されやすく、特に地方では技術者の確保が難しいケースもあります。高度な技術を要するため、計画から実施までの準備期間も長くなりがちです。
非開削工法は地盤条件によって施工の難易度や適用性が大きく変わります。
岩盤や転石が多い地盤、地下水位が高い場所、軟弱地盤など、特定の条件下では施工が困難になることがあります。また地中障害物に遭遇した場合、対処が難しくなります。
事前の地盤調査が非常に重要ですが、調査には限界があり、予期せぬ地盤状況に遭遇するリスクは常に存在します。都市部では既存埋設物との干渉リスクも考慮する必要があります。
非開削工法では、施工中に問題が発生した場合の対応が困難になりがちです。
地下で作業を行うため、掘進機の停止や管の破損が起きた場合、復旧作業は複雑で時間がかかります。最悪の場合、地上からの救助掘削が必要になり、大規模な開削工事になってしまうこともあります。
掘進中の地下水湧出や地盤沈下のリスクもあり、こうしたトラブルは工期延長や追加コストにつながります。一度開始すると途中での計画変更が難しいため、事前にリスク評価と対策を準備することが重要です。
【お役立ち情報】
コメント