お急ぎの方はコチラ
受付時間:平日9:00 - 18:00
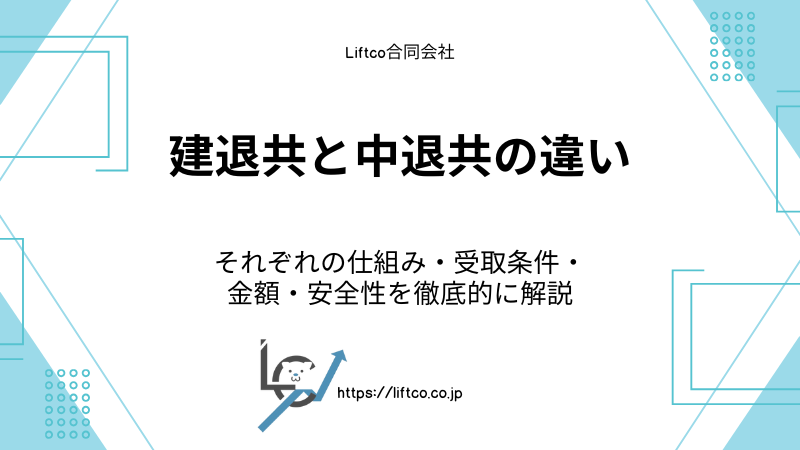
「建退共に入ってるけど、40年働いたら1,000万円くらいもらえるんじゃないの?」
そんなイメージを持っていませんか?
実はその感覚、少し危ないかもしれません。
退職金制度を正しく理解しておかないと、いざ引退するタイミングで「想像と違った…」と後悔する恐れがあります。
この記事では、建設業でよく使われる「建退共(建設業退職金共済制度)」と「中退共(中小企業退職金共済制度)」について、それぞれの仕組み・受取条件・金額・安全性を徹底的にわかりやすく解説します。

建設業に従事している方の多くが利用している退職金制度が「建退共(けんたいきょう)」です。
一般企業とは異なり、現場単位で雇用が切り替わる建設業界では、独自の仕組みが必要とされてきました。
ここでは、建退共の基本的な仕組みから、受取条件、実際の支給額、制度の安全性まで詳しく解説します。
建退共(けんたいきょう)は、建設業で働く人のために作られた退職金制度です。現場ごとに雇用先が変わるなど、継続した勤続が難しい建設業の特性に対応するために、国が設けた共済制度です。
仕組みのポイント:
一人親方のように、雇用形態が曖昧な人でも対象になる柔軟な制度です。
建退共の退職金は「会社を辞めたとき」ではなく、建設業そのものから離れたときに受け取れます。
主な請求事由は以下の通りです。
| 請求理由 | 必要書類 |
|---|---|
| 建設業を辞めた(独立・転職・無職など) | 最後の事業主の証明、雇用証明書など |
| 55歳以上になった | 住民票など |
| 病気やけがで就労不能 | 医師の診断書等 |
| 死亡時 | 戸籍謄本、遺族の住民票など |
試算条件:
この条件で建退共本部のシミュレーターを使用すると、約513万円という結果になりました。
「1,000万円くらい」と思っていた方には、少し衝撃かもしれません。
建退共の財務状況(令和元年時点):
非常に堅実な運用方針で、制度の安定性も高く、破綻の心配はほとんどありません。

建退共が建設業向けの退職金制度であるのに対し、中退共(ちゅうたいきょう)は中小企業で働く従業員のための共済制度です。
昭和34年から運用されており、多くの企業で導入されています。
この章では、中退共の制度概要、受け取りの条件、退職金の目安、安全性などを解説します。
中退共(ちゅうたいきょう)は、中小企業で働く従業員のために国が設けた退職金共済制度です。昭和34年に創設され、退職金制度の導入が難しい企業でも、簡単に管理できる仕組みが整えられています。
仕組みのポイント:
退職金が支給されるのは、会社を退職したときです。以下のケースも含まれます。
【請求の流れ】
試算条件(建退共と同条件に近づけるため):
中退共の退職金表によると、約404万円の支給額となります。
建退共と比べて少なく感じる方も多いでしょう。
なお、実際の平均掛金は7,600円で、**最も多いのは月5,000円(全体の56%)**という統計もあり、退職金額はさらに少ない可能性もあります。
中退共の財務状況(令和元年時点):
こちらも非常に安定した運用がされており、リスクはほぼありません。

建退共と中退共は、いずれも国の退職金制度でありながら、仕組みや対象者、受取額に大きな違いがあります。
この章では、それぞれの制度を横並びにして、違いをわかりやすく比較します。
自分の働き方に合った制度を選ぶための参考にしてください。
| 項目 | 建退共 | 中退共 |
|---|---|---|
| 勤務条件 | 日数による積立 | 月額掛金制 |
| 試算金額(35年) | 約513万円 | 約404万円 |
| 実態としての差 | 比較的高め | 掛金に対してやや少なめ |
※中退共は失業期間を想定せず試算しているため、より不利に見えます。
| 比較項目 | 建退共 | 中退共 |
|---|---|---|
| 積立方法 | 日数ベース(証紙) | 月額ベース(掛金) |
| 対象業種 | 建設業 | 中小企業全般 |
| 対象者 | 職人・一人親方も含む | 主に雇用された従業員 |
| 受取タイミング | 建設業を完全に離れたとき | 退職時 |
どちらも債券中心の保守的な運用で、同じ+0.32%の利回り実績です。
| 比較項目 | 建退共 | 中退共 |
|---|---|---|
| 総資産規模 | 約9,865億円 | 約4兆9,362億円 |
| 普通預金 | 約204億円 | 約1,047億円 |
| 債券比率 | 約48.3% | 約47.1% |
※建退共のほうがやや積極的な運用が見られます。
| 状況 | 向いている制度 |
|---|---|
| 建設業に長く従事する予定 | 建退共 |
| 建設業を離れる予定がある | 中退共への切替・iDeCo併用も視野に |
| 雇用が安定している中小企業勤務 | 中退共 |
| 現場が頻繁に変わる・一人親方 | 建退共 |
建退共も中退共も、長い年月をかけて積み上げる「老後資金の柱」となる制度です。
しかし、「入ってるから大丈夫」と思い込むのではなく、実際にいくらもらえるのか・いつもらえるのかを把握しておくことが重要です。
退職後に後悔しないためにも、今のうちに加入状況を確認し、場合によってはiDeCoや企業型DCといった資産形成も併用しながら、将来に備えていきましょう。
【お役立ち情報】
コメント