お急ぎの方はコチラ
受付時間:平日9:00 - 18:00
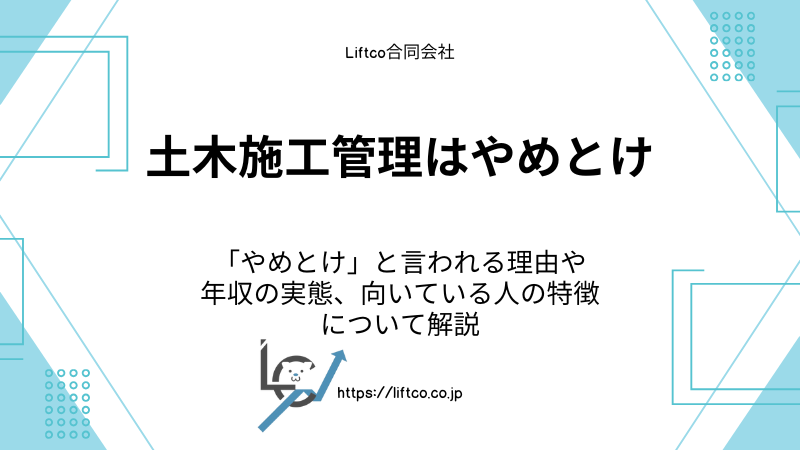
「土木施工管理への就職を検討しているが「やめとけ」という声が気になる」
「土木施工管理の仕事がきつすぎるのか知りたい」
「自分に向いているか判断したい」
このようなお悩みはありませんか?
土木施工管理は、社会インフラを支える重要な仕事です。しかし労働時間の長さや体力的な負担から「やめとけ」と言われることも多い職種です。
そこで、この記事では、土木施工管理への就職や転職を検討している方へ向けて「やめとけ」と言われる理由や年収の実態、向いている人の特徴について解説します。転職を考えている方の判断材料として、ぜひ最後までお読みください。

土木施工管理は社会インフラを支える重要な仕事ですが、「やめとけ」と言われることが多い職種でもあります。
土木施工管理が「やめとけ」と言われる理由には大きく7つあります。
それぞれ詳しく説明していきましょう。
土木施工管理の労働時間の長さが「やめとけ」と言われる最大の理由です。
厚生労働省の最新調査(2024年)によると、建設業の年間出勤日数は約238日で、全産業平均より26日も多くなっています。年間総実労働時間は約2000時間で、他産業より230時間も長い状況です。
土木工事は天候に影響されやすく、遅れを取り戻すために長時間労働が常態化しています。工事の締切が迫ると、朝7時から夜9時まで働くことも珍しくありません。
働き方改革で労働時間は7.4%削減されていますが、依然として他職種より長時間労働の傾向は変わりません。家族との時間や趣味の時間を大切にしたい人には厳しい働き方と言えるでしょう。
土木施工管理は休日が少ないことも「やめとけ」と言われる理由の一つです。
全産業では完全週休2日制の導入率が65.2%となっていますが、建設業では約4割程度にとどまっています。人材不足や工期設定の問題により、完全週休2日制の導入が困難な状況が続いているためです。
多くの土木工事は平日だけでなく、土曜日や祝日も作業を行います。施工管理者は現場の責任者として、工事がある日も雨天で現場作業が中止でも必ず現場にいなければなりません。
国土交通省の調査でも、建設業の完全週休2日制導入は大きな課題として指摘されています。年間休日が100日に満たない会社も多く、プライベートの時間を確保することがとても困難な職種です。
土木工事の締切に対するプレッシャーは、施工管理者にとって大きなストレスになります。
公共工事では国や市町村との約束で厳しい締切が決められており、遅れることは許されません。雨が続いたり機械が壊れたり、作業員が足りなくなったりする問題が起きても、決められた日までに工事を終わらせる責任があります。
締切に間に合わなくなりそうになると、夜中の作業や休日の作業を増やして対応しなければなりません。この常に追われるような状況が心の負担となり、多くの施工管理者が転職を考える原因となっています。
土木施工管理の仕事は体力的にきつく、「やめとけ」と言われる大きな理由の一つです。
施工管理者は工事現場での立ち会いが基本となるため、一日中外で過ごします。夏は40度を超える暑さの中、冬は氷点下の寒さの中で仕事をします。また、工事現場は足場が悪く、重い材料や大きな機械に囲まれた危険な場所です。
年齢を重ねるにつれて体への負担は大きくなり、50歳を過ぎても現場に立ち続けることは難しくなります。オフィスで働く仕事と比べて、体への負担が大きいことは間違いありません。
土木施工管理では大量の書類作成業務があり、これも「やめとけ」と言われる理由です。
公共工事では工事の品質や安全に関する詳しい報告書の作成が必要です。工事の計画書、品質を管理する資料、安全を管理する資料、写真をまとめた資料など、一つの工事で数百ページもの書類を作らなければなりません。
現場での仕事が終わった後の夜や休日に、これらの書類作成を行うことが多く、さらに働く時間が長くなります。コンピュータ化が進んでいない現場では手書きで作成することもあり、非効率な作業に多くの時間を取られることも珍しくありません。
土木施工管理は転勤や出張が多い仕事で、これが「やめとけ」と言われる理由の一つです。
大きな建設会社では日本全国に工事現場があるため、プロジェクトごとに違う地域で働くことが求められます。一つの工事が終わると次の現場へ移ることが普通で、2〜3年ごとに引っ越しをすることも珍しくありません。
家族がいる場合は一人だけ単身赴任をすることが多く、家庭生活に大きな影響を与えます。また、地方の工事現場では住む場所が限られており、生活環境が悪くなることもあります。安定した生活を望む人にとって、この働き方は大きな負担となります。
土木施工管理では複雑な人間関係の調整が必要で、これも「やめとけ」と言われる理由です。
施工管理者は工事を依頼した人、協力してくれる会社、現場で働く作業員など多くの人との間に立って調整する役割を担います。それぞれ違う要求や考えがあり、全ての人を満足させることは困難です。特に工事の締切が迫っている時は、各方面からの要求が集中します。
また、建設現場では昔からの慣習や体育会系の雰囲気が残っており、コミュニケーションが取りにくい場面もあります。
人間関係のストレスが原因で体調を崩したり、転職を考える人がいるのも事実です。特に現場の雰囲気や上司・同僚との関係性によって、感じる負担の大きさは大きく異なります。

土木施工管理を目指す人にとって、年収は仕事の大変さに見合うかどうかを判断する重要な要素です。「やめとけ」と言われる理由の一つに、労働時間の長さに対して年収が見合わないという声があります。
実際のところ、土木施工管理の年収水準はどの程度なのでしょうか。また、他の職種と比べて割に合う仕事と言えるのでしょうか。年収を判断する際は、金額だけでなく労働時間や将来性も含めて考えることが大切です。
土木施工管理の年収について、以下の3つの観点から詳しく見ていきましょう。
それぞれ詳しく説明していきましょう。
土木施工管理の平均年収は、働く会社の規模や経験年数によって大きく変わります。
厚生労働省の「賃金構造基本統計調査(令和5年)」によると、建設業の平均年収は約436万円となっています。年齢別では、30代が約350万円~400万円、40代後半~50代で500万円前後となっており、経験を積むことで着実に年収が上がる傾向があります。
土木施工管理者の場合、年収は400万円~600万円の範囲に収まることが多いとされています。新卒で入社した時は年収300万円程度からスタートし、資格取得や現場での実績により段階的に上がっていきます。
大手建設会社では年収700万円を超えることもありますが、中小企業では400万円台に留まることも多くあります。ただし、長時間労働を考慮すると、時給換算では高い水準とは言い切れない場合もあります。
土木施工管理の年収を他の職種と比較すると、平均的な水準にあると言えます。
| 職種 | 平均年収 | 年間労働時間 | 時給換算 |
|---|---|---|---|
| 土木施工管理 | 500万円 | 2,300時間 | 2,170円 |
| システムエンジニア | 550万円 | 2,000時間 | 2,750円 |
| 機械エンジニア | 530万円 | 2,100時間 | 2,520円 |
| 営業職 | 480万円 | 2,000時間 | 2,400円 |
| 事務職 | 400万円 | 1,900時間 | 2,110円 |
| 全職種平均 | 430万円 | 2,000時間 | 2,150円 |
この表を見ると、土木施工管理の年収は他の技術職と比べてやや低く、労働時間が長いことがわかります。時給で計算すると、事務職とほぼ同じ水準になってしまいます。年収の数字だけでなく、働く時間も含めて考えることが重要です。
土木施工管理の昇進の可能性は、資格取得と実績次第で大きく変わります。
施工管理技士の国家資格を取得することで、主任技術者や管理技術者として認められ、年収アップが期待できます。1級施工管理技士を取得すれば、年収600万円から800万円程度まで上がることも可能です。
また、現場での実績を積み重ねることで、所長や部長といった管理職に昇進するチャンスもあります。大手建設会社では年収1000万円を超える管理職も存在します。ただし、昇進には長期間の経験と高い責任が求められ、さらなる労働時間の増加を覚悟する必要があります。年収は上がりますが、その分プレッシャーも大きくなるのが現実です。

土木施工管理の仕事は人によって向き不向きがはっきりと分かれる職種です。
入職してから「こんなはずではなかった」と後悔しないためには、事前に自分がこの仕事に向いているかどうかを冷静に判断することが大切です。
土木施工管理が「やめとけ」な人の特徴には大きく3つがあります。
それぞれ詳しく説明していきましょう。
プライベートの時間を重視する人にとって、土木施工管理は「やめとけ」な職種です。
土木施工管理は労働時間が長く、休日出勤も多いため、プライベートの時間を十分に確保することが困難です。平日は朝早くから夜遅くまで働き、土曜日や祝日も工事があれば現場に出なければなりません。また、工期が迫っている時期は連続して長時間働くことも珍しくありません。
家族との時間や趣味の時間、友人との付き合いを大切にしたい人には向いていない仕事です。特に小さな子どもがいる家庭では、子育てに十分に関わることができず、家族関係に影響を与える可能性があります。ワークライフバランスを重視する人は、他の職種を検討した方が良いでしょう。
デスクワーク中心の仕事を希望する人にとって、土木施工管理は「やめとけ」な職種です。
土木施工管理の仕事は現場での立ち会いが中心となるため、一日中屋外で過ごすことが基本です。夏の暑い日も冬の寒い日も、雨の日も風の日も現場に出なければなりません。オフィスでの快適な環境での仕事を求める人には全く向いていません。
また、現場は足場が悪く、重い機械や材料に囲まれた環境です。安全に気を付けながら動き回る必要があり、常に緊張感を持って行動しなければなりません。静かで落ち着いた環境でじっくりと考えながら仕事をしたい人や、体力に自信がない人には厳しい職場環境と言えるでしょう。
転勤を避けたい人にとって、土木施工管理は「やめとけ」な職種です。
大手建設会社では全国各地に工事現場があるため、プロジェクトが変わるたびに転勤することが一般的です。2〜3年ごとに異なる地域で働くことが求められ、一つの場所に長く住み続けることは困難です。地元を離れたくない人や、特定の地域に愛着がある人には向いていません。
また、家族がいる場合は単身赴任を強いられることが多く、家族と離ればなれになる期間が長くなります。配偶者の仕事や子どもの学校の関係で家族全員での引っ越しが難しい場合、家族との時間を犠牲にすることになります。安定した生活基盤を築きたい人や、地域のコミュニティとの関係を大切にしたい人は、他の職種を選んだ方が良いでしょう。

土木施工管理は「やめとけ」と言われることが多い一方で、この仕事を続けている人たちには確かな理由があります。厳しい労働環境がある反面、他の職種では得られない大きな価値や魅力も存在するためです。
「やめとけ」と言われても土木施工管理を続ける価値には大きく3つがあります。
それぞれ詳しく説明していきましょう。
土木施工管理の最大の価値は、他の職種では味わえない大きなやりがいです。
土木工事は道路や橋、トンネルなど、多くの人が長期間使用する社会基盤を作る仕事です。自分が関わったプロジェクトが完成すると、何十年にもわたって地域の人々の生活を支え続けます。完成した時の達成感は、デスクワーク中心の仕事では得られない特別なものです。
また、一つの工事には数十人から数百人の作業員が関わり、大きなチームをまとめ上げる責任があります。困難な問題を解決し、無事に工事を完成させた時の満足感は非常に大きいものです。社会に対して直接的で目に見える貢献ができることに、強いやりがいを感じる人が多くいます。
土木施工管理は将来性のある職種で、安定した需要が見込まれる仕事です。
日本の社会基盤は高度成長期に建設されたものが多く、老朽化が進んでいます。今後は道路や橋の補修・改築工事が大量に必要となるため、土木施工管理の需要は長期間にわたって安定しています。また、災害対策や環境対応の工事も増加しており、仕事がなくなる心配はありません。
さらに、AI技術の導入により作業の効率化が進んでおり、労働環境の改善も期待されています。経験豊富な施工管理者は今後も重宝される存在であり、キャリアの安定性は高いと言えるでしょう。
土木施工管理は経験と資格次第で高収入が期待できる職種です。
施工管理技士の国家資格を取得し、現場での実績を積むことで年収は着実に上がっていきます。1級施工管理技士の資格を持つベテランの施工管理者は、年収700万円から800万円を得ることも珍しくありません。
また、独立して建設コンサルタントや施工管理の専門家として活動する道もあります。豊富な経験と人脈を活かして独立すれば、さらに高い収入を得ることも可能です。資格取得や技術向上に努力した分だけ、しっかりと収入に反映される職種と言えるでしょう。

土木施工管理について判断する際は、実際に経験した人の生の声を聞くことが最も参考になります。「やめとけ」という意見がある一方で、続けている人もいるのが現実です。
土木施工管理経験者の声には大きく2つの立場があります。
それぞれ詳しく説明していきましょう。
私自身、土木施工管理として働いていた時に、育休から復帰した後の職場環境で強いストレスを感じた経験があります。年功序列の行事で順番を外されたり、全社員に支給されていた社用車を外され公共交通での通勤を強いられるなど、不公平だと感じる対応がありました。
また、有給休暇が使えず、閑散期でも自分だけ休めない状況が続いたこともあります。これらの出来事は精神的な負担となり、「土木施工管理はやめとけ」という言葉を身をもって実感する要因となりました。
※ここで紹介するのは筆者自身の実体験であり、すべての職場に当てはまるわけではありません。
一方で、土木施工管理を続けている人からは「やりがい」を重視する声が聞かれます。
「確かに大変だが、自分が関わった道路を家族と通る時の誇らしさは何にも代えられない。この仕事でしか味わえない達成感がある」という体験談があります。また、「資格を取得してからは年収が大幅にアップし、家族を養うには十分な収入が得られている」という声もあります。
ただし、続けている人も工夫をしています。「会社選びが重要。働き方改革に取り組んでいる会社に転職してからは、残業時間が大幅に減った」「現場所長になってからは、効率的な工事管理を心がけて、部下の労働環境改善に努めている」といった、環境を変える努力をしている人が多いのが特徴です。

土木施工管理の経験を活かして転職する場合、大きく2つの方向性があります。建設業界内での職種変更か、全く異なる業界への転職かを選択することができます。
土木施工管理を辞めたい時の転職先には大きく2つがあります。
それぞれ詳しく説明していきましょう。
建設業界内での転職は、これまでの経験を最も活かしやすい選択肢です。
建設コンサルタント会社では、現場経験を活かした設計や計画業務に携わることができます。デスクワーク中心の仕事になるため、体力的な負担が大幅に軽減されます。また、建設会社の営業職では、現場の実情を理解した提案ができるため、高く評価される人材です。
設備管理会社や不動産会社での施設管理業務も人気の転職先です。建物の維持管理や改修工事の監督業務では、土木施工管理で培った技術知識が直接役立ちます。公務員として自治体の土木職に転職する人もおり、より安定した働き方を実現できます。
異業界への転職では、土木施工管理で身につけたスキルを別の分野で活用できます。
製造業の生産管理や品質管理部門では、工程管理や安全管理の経験が重宝されます。多くの人をまとめた経験は、チームリーダーやプロジェクトマネージャーとして活かすことができます。また、物流業界では配送計画や倉庫管理の業務で、効率的な作業計画を立てる能力が評価されます。
IT業界への転職も増えています。建設業界のDX化が進む中で、現場経験のあるシステムエンジニアの需要が高まっているためです。不動産業界では、建物の構造や工事に関する専門知識を活かした営業や査定業務に就く人も多くいます。
土木施工管理が「やめとけ」と言われる理由は確かに存在します。長時間労働、休日の少なさ、体力的な負担など、他の職種と比べて厳しい側面があることは事実です。
しかし、この仕事には大きなやりがいや将来性、高収入の可能性もあります。社会基盤を支える重要な役割を担い、完成時の達成感は他では味わえないものです。
最終的には個人の価値観や人生設計によって判断が分かれる職種と言えるでしょう。プライベート重視の人には向いていませんが、やりがいや収入を重視する人には魅力的な選択肢です。
土木施工管理への就職や転職を検討する際は、この記事で紹介した内容を参考に、自分にとって本当に「やめとけ」な仕事かどうかを慎重に判断することが大切です。
【お役立ち情報】
コメント