お急ぎの方はコチラ
受付時間:平日9:00 - 18:00
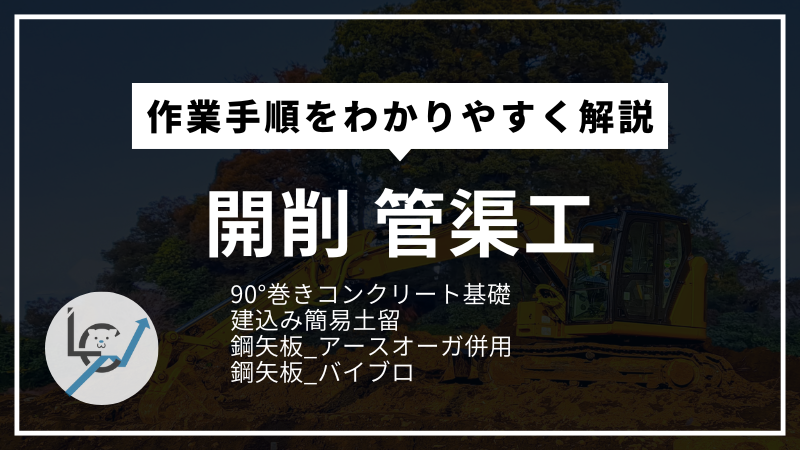
下水道などの重要な構成要素である管渠(かんきょ)の工事方法と作業手順について解説します。
管渠とは何か、その概要や種類については、こちらの記事で詳しく解説していますので、あわせてご覧ください。
管渠工事は掘削作業から始まります。バックホウなどの重機を使用して丁張りに沿って掘削を進めます。床付け作業では、管を安定して設置できるよう、掘削底面を人力で丁寧に平らに仕上げます。
過掘りしてしまった場合は、元の地盤と同等以上の材料で埋め戻し、しっかりと転圧してから仕上げます。工事中に湧水や滞水が生じた場合は、ポンプや排水溝を設けるなどして適切に排除します。
掘削中に地下埋設物を発見した場合は、工事監督者と協議し、必要に応じて人力による慎重な掘削を行い、既存の埋設物を損傷しないよう細心の注意を払います。
掘削が完了したら、管渠を支える基礎材として砕石を敷設します。バックホウで砕石を投入した後、作業員が人力で均一な厚さに広げます。その後、タンピングランマやプレートコンパクタなどの転圧機械を使用して十分に締め固めます。
基礎材がしっかりと転圧されていることで、管渠の不同沈下を防ぎ、長期的な安定性が確保されます。
90°巻きコンクリート基礎を構築するための型枠を設置します。型枠は組立てや解体が容易で、コンクリートが漏れない構造のものを使用します。
型枠内部は清掃し、離型剤を塗布してコンクリートが付着しないようにします。型枠の位置や高さは測量機器を用いて正確に設置します。
コンクリートの1次打設では、管の底部(外周)までの高さまでコンクリートを打設します。クレーン機能付きのバックホウを使用してコンクリートをホッパから流し込みます。型枠に衝撃を与えないよう注意深く作業します。
コンクリートは練り混ぜから打設完了まで1.5時間以内に作業を完了させます。一区画のコンクリートは打設が完了するまで連続して行い、表面が水平になるよう施工します。
コンクリートは高周波バイブレーターで締め固め、空気が抜けて型枠の隅々まで行き渡るようにします。バイブレーターによる横方向への不適切な移動を避けるよう注意します。
コンクリート打設後は、適切な養生を行います。表面を保水性のあるマットで覆い、養生期間中は適宜散水して湿潤状態を維持します。
低温や急激な温度変化、乾燥、衝撃などからコンクリートを保護し、一日の平均気温が4℃以下になると予想される場合は防寒養生も実施します。適切な養生によってコンクリートの強度発現を促進し、ひび割れを防止します。
管材が現場に搬入されたら、形状や寸法を確認し、ひび割れなどの損傷がないか検査します。管の設置前に接合部を布などで十分に清掃します。
管の設置はクレーン機能付きのバックホウで行い、玉掛け作業には十分注意します。丁張りに従って高さや中心線を確認しながら設置します。
管の接合時には、受口内面と挿口外面、およびゴム輪に滑剤を均一に塗布して確実に接合します。管の高さと勾配は測量機器を用いて正確に調整します。
2次打設では、管の外周90°までをコンクリートで巻きます。この90°巻きがこの工法の特徴です。コンクリートの打設や養生は1次打設と同様ですが、特に管底部など、コンクリートが充填しにくい箇所にもしっかりとコンクリートが行き渡るよう注意して施工します。
コンクリートの養生が完了したら、掘削土や流用土の中から埋戻しに適した良質の土砂を選定して埋め戻します。埋戻し作業前に、埋戻し箇所から雨水や雑物を除去します。
埋戻し材はバックホウで投入し、管渠に衝撃や過度の偏土圧を与えないよう注意します。管の中心線がずれないよう左右交互に土砂を敷き均します。
埋戻しは層状に行い、各層の仕上がり厚を30cm程度として十分に締め固めます。埋戻し幅が1.0m未満の場合はタンピングランマを、それ以上の幅では振動ローラなどの適切な転圧機械を使用します。
管渠工事を始める前に、設計図書に基づいた現場調査を行い、工程表や施工計画書を作成します。工事着工前には設計図書と現地の照合を行い、不一致がある場合は監督者と協議します。
工事区間の起点と終点を確認し、測点を設置します。また、工事区間の既存構造物や道路境界、周辺の家屋などの状態を写真で記録しておきます。
工事開始前には周辺住民への広報活動として「工事のお知らせ」を配布し、工事標板や予告板を設置します。地下埋設物の位置や種類を把握するため、試掘調査も行います。
安全対策として、交通誘導員の配置や安全設備(看板類)を設置し、車両や歩行者の安全確保に努めます。
舗装版取壊しの前に、所定の箇所を舗装カッターで切断します。切断線は事前に測量して明確に示し、過切りのないように注意します。切断後は「ノロ」(切断時に発生する泥状の廃液)を水洗いし、路面を清掃します。
舗装版の取壊しと積込みはバックホウで行い、破砕したアスファルト塊はダンプトラックに積み込んで指定の処理施設へ運搬します。工事現場の出入口には看板を設置し、交通誘導員を配置して安全確保に努めます。
バックホウで一次掘削(予掘り)を行い、ガイドポストを進行方向に対して直角に建て込みます。掘削時は地下埋設物に十分注意し、一度に大掘りしないよう心がけます。
掘削底面は不同沈下を防ぐため過度に掘りすぎないよう注意し、床付け(掘削底面の仕上げ)は人力で凹凸のないように仕上げます。掘削中に湧水や滞水が生じた場合は、ポンプや排水溝で適切に排除します。
床付け時に過掘りした場合は、同等以上の材料で埋め戻して転圧します。また、管の接合部分はあらかじめ会所掘り(接合作業スペースの確保のための追加掘削)を行っておきます。
掘削後、バックホウのクレーン機能を使用してパネルをガイドポストの両側面に挿入します。パネルは専用の吊り金具で2点吊りし、ガイドポストの溝に合わせて降ろします。パネルが床に着く少し手前で止め、寸法木を当ててパネルの内幅を固定します。
次にバックホウと人力で二次掘削と床仕上げを行い、完了後にガイドポストとパネルを押し込みます。これにより土留め壁を形成し、作業空間の安全を確保します。さらに追加のパネルをガイドポストに挿入し、パネル裏側に裏込め土を入れて垂直に固定します。
管の搬入や荷降ろしの際は、衝撃を与えないよう慎重に取り扱います。管に損傷が生じた場合は返却・交換します。
管は平らな場所に保管し、降雨や直射日光を避け、風通しの良い場所を選びます。保管時は高さ1.5m以上の段積みをせず、台木や角材を敷いて直接地面に接しないようにします。また、転がり止めを確実に行って安全を確保します。
管を据え付ける前に、亀裂やその他の欠陥がないことを確認します。据付けはバックホウのクレーン機能やクレーン付きトラックを使用し、管の重量と重心を考慮してナイロンスリングで2点吊りします。
管内部を事前に清掃し、水平器や水糸を使用して中心線や高低を確定します。管が移動や蛇行しないよう堅固に据え付けます。
管の接合部はウエスなどで清掃し、専用の止水用ゴムリングを受け口に正確に装着します。管の据付けは原則として低所から高所へ向けて行い、受け口を高所に向けます。
管の挿し口に専用の滑材を十分塗布し、レバーホイストを用いて接続します。挿入後はジョイント間隔や標線、ゴムリングの状態を全周にわたって確認してから次の管の接続に進みます。
埋戻し材料には購入砂を使用し、埋戻し前に雨水や雑物を除去します。材料はバックホウで投入し、管に衝撃や過度の偏土圧を与えないよう注意します。
埋戻しは管の中心線がずれないよう、左右交互に砂を敷き均します。特に管の側部や会所掘りした箇所は、材料が充填しにくい部分なので、砂を入れて突き棒などで左右均等に締め固めます。
管の巻出し厚さは30cm以内とし、各層ごとに締め固めます。管頂から20cmまでは人力で、それ以上はタンパ(締固め機械)で十分に締め固めます。管頂の近くは特に衝撃を与えないよう注意します。
埋戻しが下段のサポートジャッキ付近まで進んだら、パネルとガイドポストの引抜きを開始します。引抜きは締固めの厚さごとに行い、引抜いた部分への埋戻し材の充填を確実に行います。
埋戻し、転圧、パネルとガイドポストの引抜き作業を繰り返し、路床面まで埋め戻します。すべての土留め材を完全に抜き取った後、引抜いた部分の充填を確実に行います。
路床面(地表から40cm下)まで埋め戻した後、路床の仕上げを行います。路床はタンピングランマや振動ローラで転圧し、完了後に現場密度試験やプルーフローリング試験、出来形寸法の測定を行います。
次に下層路盤工を行い、RC-40(粒度調整砕石)を地表から20cm下がりまで敷設します。一層の仕上がり厚は15cm以下になるよう敷き均し、タンピングランマや振動ローラで転圧します。
下層路盤工の完了後、上層路盤工としてRM-40(粒度調整砕石)を地表から5cm下がりまで敷設し、同様に転圧します。
上層路盤完了後、舗装前に路面上の浮石やその他有害物質を除去します。舗装時は気象条件を考慮し、合材温度の低下防止や飛散防止に努めます。
縁石などの周辺構造物への飛散を防止しながらプライムコート(接着剤)を散布し、アスファルトフィニッシャや人力で舗装を行います。仕上がり面が平坦で所定の厚さと勾配になるよう敷き均します。
舗装作業中は表面を観察し、異常が認められた場合は作業を中止して原因を特定し、対策後に再開します。舗装の開放は、危険防止措置を施し、温度が50℃以下になったことを確認してから行います。
管渠工事の着手前に、設計図書に基づいた現場調査を実施し、詳細な工程表と施工計画書を作成します。工事開始前には設計図書と現地状況を照合し、不一致がある場合は監督者と協議して指示を仰ぎます。
工事区間の起点と終点を監督者立会いのもとで確認し、写真管理用の測点を設置します。また、施工区間の既存構造物や道路境界、周辺家屋の状態を写真で記録しておきます。
工事開始に先立ち、周辺住民への配慮として「工事のお知らせ」を配布し、工事標板や予告板を設置して広報活動を行います。また、地下埋設物の位置や種類を確認するため、事前に試掘調査を実施し、関係管理者と立会確認します。
安全対策として、交通誘導員の配置や各種安全設備(予告看板・警戒看板・停止位置看板など)を設置し、車両と歩行者の安全確保に努めます。
舗装版の取壊し前に、施工範囲を明確にするため、所定の箇所を舗装カッターで切断します。切断線は事前に測量して明示し、必要な幅に印をつけて過切りのないように作業します。
切断後は発生した「ノロ」(切断時の泥状の廃液)が路面に残らないよう、速やかに水洗い清掃を行い、スリップ事故を防止します。
舗装版の取壊しと積込みはバックホウで行い、破砕したアスファルト塊は規定のダンプトラックに積み込んで指定の処理施設へ運搬します。工事現場の出入口には看板を設置し、交通誘導員を配置して安全確保に努めます。
鋼矢板工法の特徴である「アースオーガ併用」では、まず鋼矢板を設置する箇所にアースオーガという大型の掘削機で先行掘削を行います。この作業により、鋼矢板の打ち込み抵抗を低減させ、施工性を向上させます。
先行掘削後、鋼矢板を設置位置に配置し、通りを確認しながら油圧式圧入機などで地中に圧入していきます。鋼矢板は高い剛性と遮水性を持つため、深い掘削や地下水位が高い場所での管渠工事に適しています。
鋼矢板の圧入完了後、バックホウで一次掘削(予掘り)を行います。掘削時は地下埋設物に十分注意し、一度に大きく掘り下げないように注意します。掘削底面は不同沈下を防ぐため過度に掘りすぎないよう注意し、床付け(掘削底面の仕上げ)は人力で凹凸のないように丁寧に仕上げます。
掘削中に地下埋設物を発見した場合は監督者と協議し、必要に応じて人力による慎重な掘削を行います。また、湧水や滞水が生じた場合は、ポンプや排水溝を設けるなどして適切に排除します。
床付け時に過掘りした場合は、元の地盤と同等以上の材料で埋め戻して転圧します。管の接合部分はあらかじめ会所掘り(接合作業スペースの確保のための追加掘削)を行っておきます。
掘削は当日中に配管から埋戻しまで完了できる範囲にとどめ、掘削幅や深さに注意して施工します。
鋼矢板による土留め壁の補強として、切梁・腹起しなどの支保工を設置します。支保工の仕様は応力計算に基づいて決定します。
掘削が下段より1.0m下がった段階で、鋼矢板にブラケットを腹起し設置位置に溶接して固定します。ブラケット設置後、ラフテレーンクレーンを使用して腹起しと切梁を設置します。
腹起しと切梁はボルトでしっかりと固定し、ジャッキの設置位置は同一方向側に偏らないよう交互に配置します。これにより、掘削時の土圧に対して安全な作業空間を確保します。
管の搬入や荷降ろしの際は、管に衝撃を与えないよう慎重に取り扱います。管に損傷が生じた場合は速やかに返却・交換します。
管は工事区域内の平らな場所を選んで保管し、降雨や直射日光を避け、風通しの良い環境を確保します。保管時は1.5m以上の高さに積み上げず、台木や角材を敷いて直接地面に接しないようにします。また、転がり防止の措置を確実に行い、安全を確保します。
管を据え付ける前に、亀裂などの欠陥がないことを確認します。据付けはバックホウのクレーン機能やクレーン付きトラックを使用し、管の重量と重心を考慮してナイロンスリングで2点吊りします。
管内部を清掃し、水平器や水糸を使用して中心線や高さを確定します。管が移動や蛇行しないよう堅固に据え付けます。
管の接合部はウエスなどで清掃し、専用の止水用ゴムリングを受け口に正確に装着します。管の据付けは原則として低所から高所へ向けて行い、受け口を高所に向けます。
管の挿し口に専用の滑材を十分塗布し、レバーホイストを用いて接続します。挿入後はジョイント間隔や標線、ゴムリングの状態を全周にわたって確認してから次の管の接続に進みます。
埋戻し材料には購入砂を使用し、作業開始前に埋戻し箇所の雨水や雑物を除去します。材料はバックホウで投入し、管に衝撃や過度の偏土圧を与えないよう注意します。
埋戻しは管の中心線がずれないよう、左右交互に砂を敷き均します。特に管の側部や会所掘りした箇所は、材料が充填しにくい部分なので、砂を入れて突き棒などで左右均等に締め固めます。
管の巻出し厚さは30cm以内とし、各層ごとに締め固めます。管頂から20cmまでは人力で、それ以上はタンパなどの機械で十分に締め固めます。管頂の近くは特に衝撃を与えないよう注意します。
切梁・腹起しなどの支保工材の撤去は、埋戻し作業と並行して行います。所定の位置まで埋め戻した後、ラフテレーンクレーンを使用して支保工を撤去します。
埋戻し材料の投入はバックホウで行い、購入砂を使用します。埋戻し前に埋戻し箇所の雨水や雑物を除去します。
転圧は一層の厚さが30cmを超えない範囲で、振動ローラやタンピングランマを使用して締め固めます。不等沈下が生じないよう丁寧に転圧作業を行います。
埋戻しが完了したら、油圧式杭圧入引抜機を設置して鋼矢板の引抜きを行います。引抜き作業は打ち込み時と同様に油圧式杭圧入引抜機で行い、鋼矢板の吊り込みはラフテレーンクレーンを使用します。
鋼矢板の引抜き後には空洞が生じるため、砂などで確実に充填して地盤沈下を防止します。空隙による地盤沈下の影響が大きいと判断される場合は、監督者と協議して対策を講じます。引抜き作業は管に影響を与えないよう細心の注意を払います。
路床面(地表から40cm下)まで埋め戻した後、路床の仕上げを行います。路床はタンピングランマや振動ローラで転圧し、完了後に現場密度試験やプルーフローリング試験、出来形寸法の測定を行います。
次に下層路盤工を行い、RC-40(粒度調整砕石)を地表から20cm下がりまで敷設します。一層の仕上がり厚は15cm以下になるよう敷き均し、十分に転圧します。締固めは現場密度試験で求めた最適含水比付近で所定の締固め度になるよう行います。
下層路盤工の完了後、上層路盤工としてRM-40(粒度調整砕石)を地表から5cm下がりまで敷設し、同様に転圧します。
上層路盤完了後、舗装前に路面上の浮石やその他有害物質を除去します。舗装時は気象条件を考慮し、合材温度の低下防止や飛散防止に努めます。
縁石などの周辺構造物への飛散を防止しながらプライムコートを散布し、アスファルトフィニッシャや人力で舗装を行います。仕上がり面が平坦で所定の厚さと勾配になるよう敷き均します。
舗装作業中は表面を観察し、異常が認められた場合は作業を中止して原因を特定し、対策後に再開します。舗装の開放は、危険防止措置を施し、温度が50℃以下になったことを確認してから行います。
管渠工事の着手前に、設計図書に基づいた現場調査を実施し、詳細な工程表と施工計画書を作成します。工事開始前には設計図書と現地状況を照合し、不一致がある場合は監督者と協議して指示を仰ぎます。
工事区間の起点と終点を監督者立会いのもとで確認し、写真管理用の測点を設置します。また、施工区間の既存構造物や道路境界、周辺家屋の状態を写真で記録しておきます。
工事開始に先立ち、周辺住民への配慮として「工事のお知らせ」を配布し、工事標板や予告板を設置して広報活動を行います。また、地下埋設物の位置や種類を確認するため、事前に試掘調査を実施し、関係管理者と立会確認します。
安全対策として、交通誘導員の配置や各種安全設備(予告看板・警戒看板・停止位置看板など)を設置し、車両と歩行者の安全確保に努めます。
舗装版の取壊し前に、施工範囲を明確にするため、所定の箇所を舗装カッターで切断します。切断線は事前に測量して明示し、必要な幅に印をつけて過切りのないように作業します。
切断後は発生した「ノロ」(切断時の泥状の廃液)が路面に残らないよう、速やかに水洗い清掃を行い、スリップ事故を防止します。
舗装版の取壊しと積込みはバックホウで行い、破砕したアスファルト塊は規定のダンプトラックに積み込んで指定の処理施設へ運搬します。工事現場の出入口には看板を設置し、交通誘導員を配置して安全確保に努めます。
鋼矢板_バイブロ工法では、ラフテレーンクレーンとバイブロハンマーを組み合わせて鋼矢板の打込みを行います。まず打込み箇所に施工ラインを設定し、鋼矢板打込み定規が設置できるよう所定の高さで床均しを行います。
ラフテレーンクレーンの親ワイヤーにバイブロハンマーを装着し、準備を整えます。補助ワイヤーロープで鋼矢板を吊り上げ、バイブロハンマーのチャックでつかみます。鋼矢板を所定の位置に垂直に立て込み、バイブロハンマーを起動して打ち込みます。
安全のため、バイブロハンマー作動時も鋼矢板を吊った補助ワイヤーロープは緩める程度にしておきます。バイブロハンマーの重量で鋼矢板に曲がりや亀裂が発生しないよう、ハンマーの重量を鋼矢板に全て預けないように十分注意します。
この工法の特徴は、バイブロハンマーによる振動で鋼矢板と地盤の摩擦抵抗を低減させ、効率的に鋼矢板を打ち込むことができる点にあります。ただし、振動による周辺環境への影響にも注意が必要です。
鋼矢板の打込み完了後、バックホウで一次掘削(予掘り)を行います。掘削時は地下埋設物に十分注意し、一度に大きく掘り下げないように注意します。掘削底面は不同沈下を防ぐため過度に掘りすぎないよう注意し、床付け(掘削底面の仕上げ)は人力で凹凸のないように丁寧に仕上げます。
掘削中に地下埋設物を発見した場合は監督者と協議し、必要に応じて人力による慎重な掘削を行います。また、湧水や滞水が生じた場合は、ポンプや排水溝を設けるなどして適切に排除します。
床付け時に過掘りした場合は、元の地盤と同等以上の材料で埋め戻して転圧します。管の接合部分はあらかじめ会所掘り(接合作業スペースの確保のための追加掘削)を行っておきます。
掘削は当日中に配管から埋戻しまで完了できる範囲にとどめ、掘削幅や深さに注意して施工します。
鋼矢板による土留め壁の補強として、切梁・腹起しなどの支保工を設置します。支保工の仕様は応力計算に基づいて決定します。
掘削が下段より1.0m下がった段階で、鋼矢板にブラケットを腹起し設置位置に溶接して固定します。ブラケット設置後、ラフテレーンクレーンを使用して腹起しと切梁を設置します。
腹起しと切梁はボルトでしっかりと固定し、ジャッキの設置位置は同一方向側に偏らないよう交互に配置します。これにより、掘削時の土圧に対して安全な作業空間を確保します。
管の搬入や荷降ろしの際は、管に衝撃を与えないよう慎重に取り扱います。管に損傷が生じた場合は速やかに返却・交換します。
管は工事区域内の平らな場所を選んで保管し、降雨や直射日光を避け、風通しの良い環境を確保します。保管時は1.5m以上の高さに積み上げず、台木や角材を敷いて直接地面に接しないようにします。また、転がり防止の措置を確実に行い、安全を確保します。
管を据え付ける前に、亀裂などの欠陥がないことを確認します。据付けはバックホウのクレーン機能やクレーン付きトラックを使用し、管の重量と重心を考慮してナイロンスリングで2点吊りします。
管内部を清掃し、水平器や水糸を使用して中心線や高さを確定します。管が移動や蛇行しないよう堅固に据え付けます。
管の接合部はウエスなどで清掃し、専用の止水用ゴムリングを受け口に正確に装着します。管の据付けは原則として低所から高所へ向けて行い、受け口を高所に向けます。
管の挿し口に専用の滑材を十分塗布し、レバーホイストを用いて接続します。挿入後はジョイント間隔や標線、ゴムリングの状態を全周にわたって確認してから次の管の接続に進みます。
埋戻し材料には購入砂を使用し、作業開始前に埋戻し箇所の雨水や雑物を除去します。材料はバックホウで投入し、管に衝撃や過度の偏土圧を与えないよう注意します。
埋戻しは管の中心線がずれないよう、左右交互に砂を敷き均します。特に管の側部や会所掘りした箇所は、材料が充填しにくい部分なので、砂を入れて突き棒などで左右均等に締め固めます。
管の巻出し厚さは30cm以内とし、各層ごとに締め固めます。管頂から20cmまでは人力で、それ以上はタンパなどの機械で十分に締め固めます。管頂の近くは特に衝撃を与えないよう注意します。
切梁・腹起しなどの支保工材の撤去は、埋戻し作業と並行して行います。所定の位置まで埋め戻した後、ラフテレーンクレーンを使用して支保工を撤去します。
埋戻し材料の投入はバックホウで行い、購入砂を使用します。埋戻し前に埋戻し箇所の雨水や雑物を除去します。
転圧は一層の厚さが30cmを超えない範囲で、振動ローラやタンピングランマを使用して締め固めます。不等沈下が生じないよう丁寧に転圧作業を行います。
埋戻しが完了したら、油圧式杭圧入引抜機を設置して鋼矢板の引抜きを行います。引抜き作業は打ち込み時と同様に油圧式杭圧入引抜機で行い、鋼矢板の吊り込みはラフテレーンクレーンを使用します。
鋼矢板の引抜き後には空洞が生じるため、砂などで確実に充填して地盤沈下を防止します。空隙による地盤沈下の影響が大きいと判断される場合は、監督者と協議して対策を講じます。引抜き作業は管に影響を与えないよう細心の注意を払います。
バイブロ工法で打ち込んだ鋼矢板の引抜きも、同様に振動を利用して効率的に行うことができますが、周辺構造物への影響に十分注意する必要があります。
路床面(地表から40cm下)まで埋め戻した後、路床の仕上げを行います。路床はタンピングランマや振動ローラで転圧し、完了後に現場密度試験やプルーフローリング試験、出来形寸法の測定を行います。
次に下層路盤工を行い、RC-40(粒度調整砕石)を地表から20cm下がりまで敷設します。一層の仕上がり厚は15cm以下になるよう敷き均し、十分に転圧します。締固めは現場密度試験で求めた最適含水比付近で所定の締固め度になるよう行います。
下層路盤工の完了後、上層路盤工としてRM-40(粒度調整砕石)を地表から5cm下がりまで敷設し、同様に転圧します。
上層路盤完了後、舗装前に路面上の浮石やその他有害物質を除去します。舗装時は気象条件を考慮し、合材温度の低下防止や飛散防止に努めます。
縁石などの周辺構造物への飛散を防止しながらプライムコートを散布し、アスファルトフィニッシャや人力で舗装を行います。仕上がり面が平坦で所定の厚さと勾配になるよう敷き均します。
舗装作業中は表面を観察し、異常が認められた場合は作業を中止して原因を特定し、対策後に再開します。舗装の開放は、危険防止措置を施し、温度が50℃以下になったことを確認してから行います。
【お役立ち情報】
コメント