お急ぎの方はコチラ
受付時間:平日9:00 - 18:00
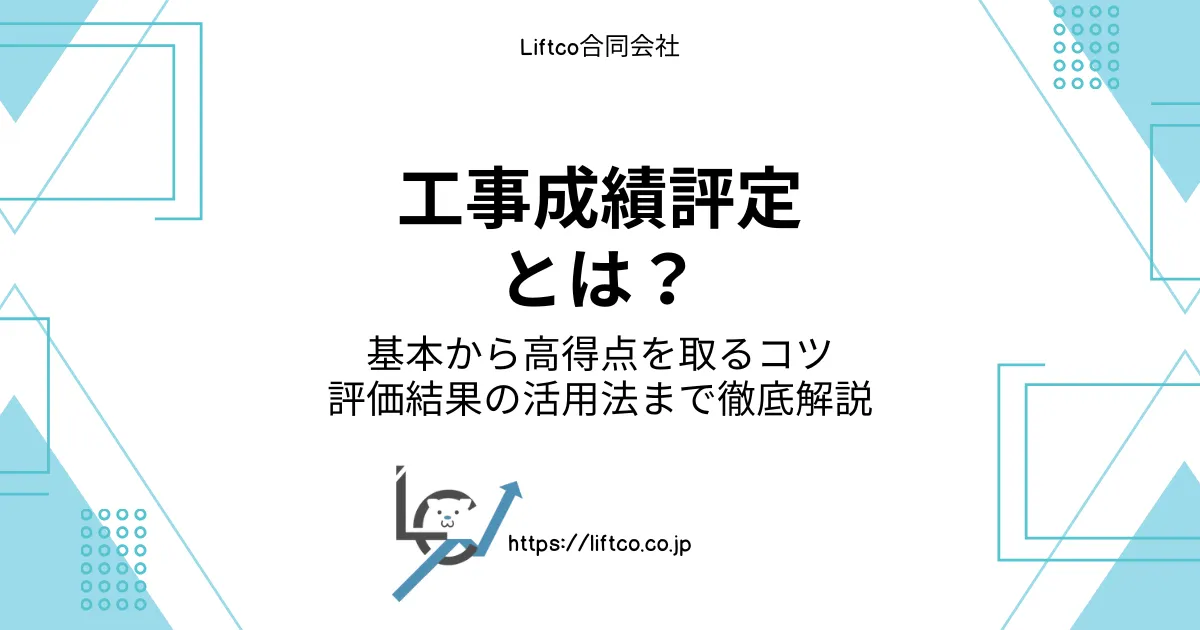
「工事成績評定の仕組みがわからない」
「高得点を取るにはどうすればいいのか」
「評価結果をどう活用すればいいのだろう」
このようなお悩みはありませんか?
工事成績評定とは、公共工事完了後に発注者が受注者の施工内容を評価する制度です。この評価は企業の格付けや入札参加資格に直接影響するため、建設業界で極めて重要な指標となっています。
そこで、この記事では建設業に携わる方へ向けて工事成績評定の基本から高得点を取るコツ、評価結果の活用法まで徹底解説します。企業価値向上のための参考として、ぜひ最後までお読みください。

工事成績評定とは、公共工事の完成後に発注者(国や地方自治体など)が受注者(建設会社)の工事内容を評価する制度です。この評価制度は建設業界において非常に重要な役割を果たしています。
それぞれの内容について詳しく説明していきましょう。
工事成績評定が行われる主な背景には、公共工事の品質確保と建設業界全体の技術力向上があります。
公共工事は税金を使って行われるため、適正な品質と価格のバランスが求められます。工事成績評定制度は、この品質管理を客観的に行うための仕組みとして導入されました。
また、この制度は単に評価するだけでなく、建設会社の技術力向上を促す役割も担っています。評定結果をフィードバックすることで、企業は自社の弱点を把握し、改善することができます。
さらに、工事成績評定は優良な建設会社を選定するための指標としても活用されています。発注者側は過去の評定結果を参考に、信頼できる業者を選ぶことができるのです。
工事成績評定の結果は、建設会社の格付けや将来の入札参加資格に直接影響します。
多くの公共発注機関では、過去2年間の工事成績評定の平均点を企業の格付け評価に組み込んでいます。高い評定点を獲得している企業は上位ランクに格付けされ、大型案件の入札参加資格を得やすくなります。
逆に、低い評定点が続くと、一定期間入札参加資格が制限されることもあります。特に65点未満の評価が複数回続くと、指名停止などのペナルティを受ける可能性があるのです。
また、総合評価方式の入札では、過去の工事成績評定点が加点対象となることが多く、高得点を維持している企業は落札確率が高まります。このように工事成績評定は企業の受注機会に大きな影響を与える重要な指標なのです。
工事成績評定は、工事の完成・引渡し後に実施されます。評価の流れと方法について見ていきましょう。
まず、工事の検査官(監督員)が現場確認と書類審査を行います。この際、出来形、品質、工程管理、安全管理などの項目について細かくチェックします。
評価は通常、複数の担当者によって行われ、主任監督員、総括監督員などが関わることで、評価の客観性を確保しています。各評価項目ごとに点数がつけられ、それらを合計して総合点が算出されます。
評価結果は通常、工事完了から1~2ヶ月程度で通知されます。国土交通省の工事では、評定結果を受注者に通知する義務があり、評価内容に対する説明請求の機会も設けられています。
工事成績評定の点数は100点満点で評価され、一般的に70点台が標準的な評価とされています。点数の意味とその見方について解説します。
| 評定点数 | 評価レベル | 意味 |
|---|---|---|
| 90点以上 | 優良 | 特に優れた成績 |
| 80点台 | 良好 | 標準を上回る成績 |
| 70点台 | 標準 | 要求水準を満たす成績 |
| 60点台 | 要注意 | 改善を要する部分がある |
| 60点未満 | 不良 | 大幅な改善が必要 |
評定通知書には点数だけでなく、所見欄も重要な情報源です。所見欄には評価者からの具体的なコメントが記載されており、良かった点や改善すべき点が明記されています。
例えば「丁寧な仕上がりで品質が高い」「地域住民とのコミュニケーションが優れている」といった評価や、「書類の不備が多い」「安全管理体制に改善の余地あり」などの指摘が記載されます。
この所見は次回の工事に向けた具体的な改善点として活用できますので、点数と合わせて注意深く確認することが大切です。

工事成績評定の平均点は発注機関やエリアによって若干の差がありますが、全国的な傾向と優良とされる基準には一定のパターンがあります。平均点や優良基準を理解することで、自社の評価位置を把握することができます。
それでは各項目について詳しく見ていきましょう。
工事成績評定の全国的な平均点は、近年75点前後で推移しています。この数値は公共工事の品質向上とともに緩やかな上昇傾向にあります。
国土交通省が発注する直轄工事では、令和元年度の平均点が約75.8点、令和2年度が約76.2点と報告されています。地方自治体の発注工事でも、概ね74〜76点の範囲に平均点が集中しています。
工種別に見ると、一般的に橋梁やトンネルなどの難易度の高い工事では、専門性の高い業者が担当するため平均点がやや高くなる傾向があります。一方、一般土木や舗装工事では競争が激しく、平均点は標準的な水準となっています。
地域別では、都市部と地方で若干の差が見られることもありますが、その差は年々縮小傾向にあります。工事成績評定制度の浸透により、全国的に一定の品質水準が確保されつつあるといえるでしょう。
工事成績評定において「優良」とされる基準点は、多くの発注機関で80点以上に設定されています。特に優れた工事については85点以上、さらに90点以上ともなると「特に優秀」と評価されます。
国土交通省の場合、80点以上の工事は「優良工事」として認定される可能性が高くなります。ただし、発注事務所によっては82点以上を基準としているケースもあります。
地方自治体では、78点以上を優良の基準とするところもあれば、82点以上を要求するところもあり、発注機関ごとに若干の違いがあります。一般的には以下のような区分が多く見られます。
| 評定点数 | 評価区分 | 認定状況 |
|---|---|---|
| 90点以上 | 特に優秀 | 表彰対象となることが多い |
| 85〜89点 | 極めて優良 | 上位の優良工事として認定 |
| 80〜84点 | 優良 | 優良工事として認定 |
| 75〜79点 | やや優良 | 平均以上の評価 |
| 70〜74点 | 標準 | 標準的な評価 |
優良認定のボーダーラインを超えるためには、基本的な工事品質の確保はもちろん、創意工夫や地域貢献などの付加価値が求められます。特に安全管理や環境配慮、工程管理の的確さなどが高く評価されるポイントとなっています。
高い工事成績評定点を獲得すると、表彰やランキングにつながる可能性が高まります。これらの評価は企業の信頼性と技術力を対外的にアピールする重要な指標となります。
国土交通省直轄工事では、80点以上の工事の中から「優良工事施工者」として表彰される制度があります。特に85点以上の高得点を獲得した工事は、優先的に表彰候補となることが多いです。
また、多くの地方自治体でも独自の表彰制度を設けており、高得点工事の施工者を「優良建設業者」として認定・公表しています。これらの表彰は次回以降の総合評価方式入札における加点対象となるため、企業にとって大きなメリットとなります。
評定点に基づくランキングも、業界内での企業評価に大きな影響を与えています。国土交通省や業界紙などが定期的に公表する「工事成績優良企業ランキング」は、取引先や金融機関からの評価にも反映されます。
特に複数年にわたって高得点を維持している企業は、「特定建設業者」や「優良工事施工業者」として認定され、大型案件への参加資格が優遇されることもあります。このように工事成績評定は単なる点数以上の価値を持ち、企業の成長戦略に直結する重要な指標となっているのです。

工事成績評定では複数の評価項目に基づいて総合的に採点が行われます。
各項目の評価ポイントを理解し、適切に対応することで高得点を目指すことができます。
それぞれの評価項目について詳しく見ていきましょう。
出来形の評価では、測定値が設計値に対してどれだけ正確に施工されているかが重要です。特に基準高、幅、厚さなどの主要な寸法の精度が厳しくチェックされます。具体的な評価指標として、測定値の誤差が規格値の50%以内であるかが重視されます。この50%以内という数値は、高評価を得るための1つの重要な目安となっています。許容範囲を超える誤差があると大幅な減点対象となります。
減点されやすい事例として、「測定箇所の不足」が挙げられます。規定された箇所数の測定が行われていない場合、データ不足として評価が下がります。また、「測定値のバラつき」も減点要因となり、施工精度の均一性が求められます。
さらに、出来形管理図表の作成不備や写真管理の不足も減点対象となります。特に出来形管理図表は、測定値と設計値の対比、規格値との関係が明確に示されていることが重要です。写真については、測定状況がわかる写真や出来形の確認写真が適切に整理されていることが求められます。
品質の評価では、材料や施工の品質が設計図書の要求を満たしているかどうかが審査されます。さらに、品質を確保するための管理体制も重要な評価ポイントとなります。
材料の品質については、使用材料の品質証明書や試験結果が適切に整理され、要求性能を満たしていることが必要です。特にコンクリートや鉄筋、アスファルト合材などの主要材料については、品質データの整理状況が厳しく評価されます。
施工品質では、各工種の要求品質を満たしているかが確認されます。例えば、コンクリート構造物であれば強度試験結果、舗装工事であれば平坦性や密度などの品質特性が評価対象となります。
品質管理体制においては、品質管理計画の適切さと実施状況が重視されます。具体的には、品質管理のための組織体制、検査体制、不具合発生時の対応体制などが評価されます。また、日常的な品質チェックの実施記録や、協力業者への品質指導状況なども評価対象となっています。
工程管理の評価では、工事全体の進捗状況を適切に管理し、計画工程内に工事を完了させる能力が問われます。工程管理は評定点に大きく影響する重要項目の一つです。
評価のポイントとなるのは、まず施工計画と実施工程の整合性です。当初計画した工程表と実際の進捗状況の比較が適切に行われ、差異が生じた場合の対応策が明確に示されていることが重要です。
また、工程の遅延要因への対応力も重視されます。天候不良や予期せぬ地中障害物の発見など、工事中に発生する様々な課題に対して、迅速かつ適切な対応ができているかがチェックされます。
さらに、工程管理のための会議体の運営状況や、工程表の更新・管理状況も評価対象となります。定期的な工程会議の開催記録や、詳細な工程表の更新履歴が確認されます。
高評価を得るための対策としては、工程管理ソフトの活用による視覚的な進捗管理や、クリティカルパスの明確化と重点管理などが効果的です。また、工程遅延のリスク分析と事前対策の立案、余裕を持った工程計画の策定なども有効な手段となります。
安全管理の評価は、作業員の安全確保と第三者への危害防止に関する取り組みが対象となります。労働災害の防止は社会的責任であるとともに、工事成績評定にも大きく影響します。
評価の主な観点は、安全管理体制の整備状況です。安全衛生責任者の選任、安全パトロールの実施状況、安全教育の実施記録などが確認されます。特に安全パトロールでは、指摘事項とその改善状況の記録が重要です。
また、安全対策の実施状況も重視されます。適切な安全設備・保護具の設置・使用状況、危険作業に対する特別な安全対策の実施状況などがチェックポイントとなります。
さらに、第三者への安全対策として、工事現場周辺の安全確保措置や交通誘導員の配置状況、近隣住民への配慮なども評価対象です。特に通学路や交通量の多い道路に面した現場では、より厳しいチェックが行われます。
高評価を得るためには、法令遵守の徹底はもちろん、現場独自の安全活動や創意工夫された安全対策の実施が効果的です。また、協力業者を含めた安全意識の向上活動や、ヒヤリハット事例の収集・分析による予防活動なども評価されます。
工事成績評定では、主要な評価項目以外にも様々な観点から評価が行われます。特に近年重視されているのが、環境配慮と地域対応の取り組みです。
環境配慮の評価では、騒音・振動対策、粉じん対策、水質汚濁防止対策などの基本的な環境保全措置の実施状況がチェックされます。さらに、CO2削減の取り組みやリサイクル材の積極的な活用、生物多様性への配慮なども高く評価されるポイントとなっています。
地域対応の評価では、地域住民とのコミュニケーション状況が重視されます。工事説明会の開催状況、苦情・要望への対応状況、工事情報の提供方法などがチェックされます。特に苦情発生時の迅速かつ誠実な対応は、評価に大きく影響します。
また、地域貢献活動として、現場周辺の清掃活動や地域行事への参加、地元雇用・地元調達の状況なども評価対象となっています。これらの活動は「社会性」の評価項目として反映されることが多いです。
その他、新技術・新工法の積極的な活用や、情報化施工の導入なども「創意工夫」として評価対象となります。これらは加点要素として働くため、高得点を目指す上では積極的に取り組むことが重要です。

工事成績評定で高得点を取るには、減点防止と積極的な加点の両方が重要です。チーム全体の連携も評価に直結します。
それぞれのポイントを簡潔に解説します。
減点を防ぐためには書類と現場の基本管理が重要です。
施工計画書は具体的かつ実行可能な内容にしましょう。工事写真は特に不可視部分を計画的に撮影し、整理することが必須です。
現場管理では日々の進捗記録と問題発生時の対応記録を残しましょう。資材管理や整理整頓も評価対象となります。
減点防止のチェックポイント:
基本点確保に加え、積極的な加点の工夫も重要です。
新技術・新工法の導入はNETIS登録技術の活用などが評価されます。現場独自の工夫も高評価につながります。
地域貢献活動として、周辺清掃や交通安全活動、地域行事への参加なども評価対象です。
環境配慮では、CO2削減やリサイクル材活用など環境負荷低減の取り組みが重要です。
加点のポイント:
組織としての総合力が高評価につながります。
現場内では定期的な会議で情報共有を図り、問題発生時の早期報告体制を整えましょう。
発注者とは進捗報告や協議事項への迅速対応で信頼関係を構築します。設計変更時の早期情報提供も重要です。
地域住民や関係機関との良好な関係づくりも忘れずに行いましょう。
チーム力強化のポイント:

工事成績評定の点数は企業の強みや弱みを客観的に示す重要な指標です。自社だけでなく他社の点数も確認し、業界内での位置づけを把握することが成長戦略に役立ちます。
それぞれの方法について解説します。
工事成績評定の点数確認は、発注機関ごとに方法が異なります。
自社の点数は、工事完了後に発注機関から送付される「工事成績評定通知書」で確認できます。この通知書には総合点のほか、項目別の評価点や所見も記載されています。
国土交通省の工事では、評定結果に疑義がある場合、通知から2週間以内に説明を求めることができます。この制度を活用して評価の根拠を確認することも大切です。
他社の点数確認には、公共発注機関のホームページを活用します。国土交通省や多くの自治体では、工事成績評定の結果を公表しています。検索システムで工種や地域、期間を指定して検索すると、該当する工事の評定点を確認できます。
また、情報公開制度を利用して特定の工事の評定点を請求することも可能です。ただし、詳細な評価内容までは公開されないことが一般的です。
公表されている評定情報は様々な形で入手・活用できます。
情報入手の主な方法:
これらの情報は以下のように活用できます。
多くの自治体や発注機関では、工事成績評定結果を公式ホームページで公開しています。例えば、佐渡市では80点以上の工事について、工事名や請負業者名、評定点をホームページで公表しており、契約検査室で通知書の写しも閲覧可能です。
建設業界紙や専門誌では、工事成績評定結果を集計・分析した記事が掲載されることがあります。例えば、県土整備局が公表した集計結果が業界紙に取り上げられています。
工事成績対策講習会などでは、竣工検査や設計変更に関する具体的な事例が紹介されることがあります。これらのセミナーは高得点獲得のためのノウハウを学ぶ場として提供されています。
建設業協会などが会員向けに提供する情報サービスも有効な手段です。例えば、宮崎県建設業協会は助成事業として講習会を開催し、具体的な工事成績評価対策を学べる機会を提供しています。
評価結果を単に記録するだけでなく、詳細に分析して今後の改善に活かすことが重要です。
評定通知書に記載された項目別の評価点を分析し、自社の強みと弱みを把握します。特に低評価の項目については、具体的な改善策を検討します。
評定通知書の所見欄には、評価者からの具体的なコメントが記載されています。これを社内で共有し、良かった点は標準化し、指摘された点は早急に改善策を講じることが大切です。
複数年にわたる評定結果を時系列で分析し、改善の進捗や新たな課題の発生を確認します。特に同じ指摘が繰り返されている場合は、根本的な対策が必要です。
課題改善のステップ:
このサイクルを継続することで、工事成績評定の点数向上だけでなく、企業としての技術力と現場力の向上にもつながります。評価結果を組織の成長機会として積極的に活用することが、建設業界での競争力強化の鍵となるのです。
工事成績評定は単なる点数ではなく、建設企業の技術力や信頼性を示す重要な指標です。高評価を得ることで企業の格付けが上がり、入札機会の拡大や受注確率の向上につながります。
評定では出来形、品質、工程管理、安全管理など多角的な視点から評価されるため、総合的な現場力が問われます。全国平均は75点前後で、80点以上が優良と認められる目安となっています。
高得点を目指すには基本的な減点防止策を徹底し、創意工夫や地域貢献など加点要素を積極的に取り入れることが大切です。また、評定結果を分析して改善につなげる継続的な取り組みも欠かせません。
工事成績評定は建設企業の成長と発展を支える羅針盤です。この制度を正しく理解し、戦略的に活用することで、企業価値の向上と持続的な成長につなげていきましょう。
【お役立ち情報】
コメント