お急ぎの方はコチラ
受付時間:平日9:00 - 18:00
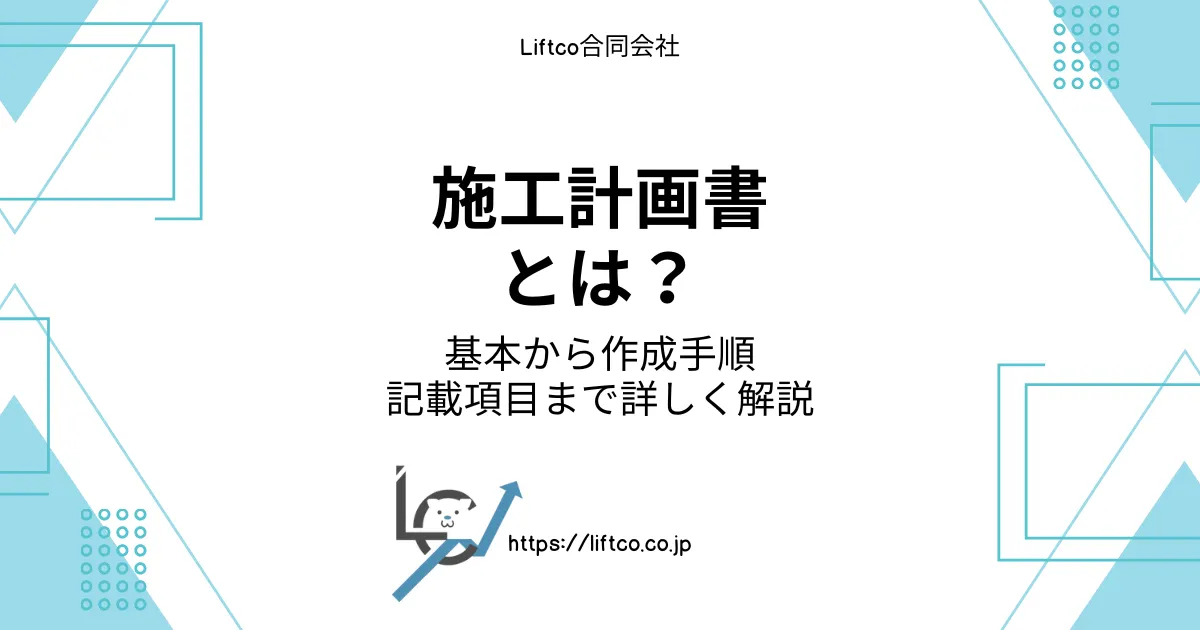
「施工計画書ってどうやって作ればいいのだろう」
「施工計画書は何を書けばいいのか分からない」
このようなお悩みはありませんか?
施工計画書とは、工事の実施方法や安全対策を詳細に記した計画書です。適切に作成することで、工事の安全性確保や品質向上、効率化が図れます。
そこで、この記事では、建設業に携わる方へ向けて施工計画書の基本から作成手順、記載項目まで詳しく解説します。法的根拠や提出義務についても触れていますので、初めて施工計画書を作成する方はぜひ最後までお読みください。

施工計画書とは、建設工事を安全かつ効率的に進めるために作成される計画書です。
工事の目的、施工方法、使用する機材、工程、管理体制などを記載し、関係者全員で情報を共有する役割を持ちます。
この記事では、施工計画書の定義や目的について詳しく解説します。
施工計画書の目的は、工事を安全かつ効率的に進めるための具体的な計画を明文化することにあります。
発注者と施工者の間で、工事の進め方について共通認識を持つことができます。また、工事中に発生する可能性のある問題を事前に想定し、対策を講じることができるのも大きな利点です。
施工計画書は単なる形式的な書類ではなく、実際の工事を円滑に進めるための重要なツールとして機能します。特に大規模な工事では、関係者全員が同じ情報を共有できる貴重な資料となります。
施工計画書と混同されやすいのが施工要領書です。両者は似ていますが、明確な違いがあります。
| 項目 | 施工計画書 | 施工要領書 |
|---|---|---|
| 内容 | 工事全体の計画 | 具体的な作業手順 |
| 範囲 | 工事全体を網羅 | 特定の作業に焦点 |
| 目的 | 全体管理と安全確保 | 品質確保と作業効率化 |
| 提出義務 | 法的義務あり | 発注者の要請による |
施工計画書が「何をするか」を示すのに対し、施工要領書は「どのように行うか」の詳細を記します。両方の書類を適切に作成することで、工事の質と効率を高めることができます。
施工計画書が必要な理由は、主に以下の3点です。
安全性の確保では、事前に危険因子を洗い出し、適切な安全対策を計画することで事故を防止します。品質の確保については、適切な施工手順や品質管理方法を明確にすることで、要求される品質基準を満たす工事が可能になります。効率化の実現では、人員配置や資材調達、工程管理などを計画的に行うことで、無駄のない効率的な施工が実現できます。
法的な義務としての側面だけでなく、実務上も非常に重要な役割を持つ書類なのです。
弊社では土木専門で施工管理のサポートを行っています。施工計画書の作成で困っている人、すぐ作らなければならないのに人手が足りない人などは以下からお問い合わせください。

施工計画書は全ての工事で必要というわけではありません。しかし、特定の条件を満たす工事では法律によって作成が義務付けられています。
主に以下のような場合に施工計画書の作成が必要となります。
これらの条件に当てはまる工事を請け負った場合は、施工計画書の作成が必須です。作成を怠ると法令違反となる可能性があるため、注意が必要です。
建設業法第24条の8により、請負代金が500万円以上の工事では施工計画書の作成が義務付けられています。
この「500万円」という基準は、工事の規模を表す一つの目安とされています。一般的に500万円以上の工事は、一定の規模と複雑さを持つと考えられているためです。
ただし、500万円未満の工事であっても、安全管理や品質確保の観点から自主的に施工計画書を作成することは大いに推奨されています。特に危険を伴う作業がある場合は、金額に関わらず施工計画書を用意することが望ましいでしょう。
施工計画書の提出先は、基本的には発注者または発注者の代理人(監理技術者など)となります。
提出期限については、工事着工前に提出するのが原則です。具体的な期限は契約書や特記仕様書に記載されていることが多く、一般的には以下のタイミングが目安となります。
これらの期限を守らないと、工事の着工が認められないケースもあります。また、提出後に発注者から修正を求められる場合もあるため、余裕を持ったスケジュールで作成することが重要です。
提出方法は、紙の書類として提出するケースが多いですが、最近ではデータでの提出を認める発注者も増えています。提出方法についても事前に確認しておくと良いでしょう。

施工計画書の作成は、単に書類を埋めるだけでなく、実際の工事を具体的にイメージしながら行う必要があります。
ここでは効率的かつ確実に施工計画書を作成するための5つのステップを解説します。これらの手順に従うことで、発注者に認められる質の高い施工計画書を作成することができます。
まず全体の流れを把握しましょう。その後、各ステップの詳細を確認していきます。
施工計画書作成の第一歩は、工事に関する書類の確認です。
確認すべき主な書類は以下の通りです。
これらの書類から、工事の目的や規模、特殊条件などを正確に把握します。特に特記仕様書には、施工計画書に記載すべき特定の要件が示されていることがあるため、注意深く確認しましょう。
書類の内容に不明点がある場合は、この段階で洗い出しておくことが重要です。後の工程でトラブルを防ぐことができます。
書類確認の次は、実際の現場状況を確認する段階です。
現場確認では以下のポイントをチェックします。
現場状況を確認することで、書類だけでは見えてこない実際の条件を施工計画に反映させることができます。特に安全対策や環境対策は、現場の状況に応じた具体的な計画が求められます。
現場確認の際には写真撮影も行い、施工計画書作成の参考資料として活用するとよいでしょう。
現場確認後は、発注者や監理者との協議を行います。
この協議では以下の内容を確認します。
発注者との協議は、施工計画書作成の方向性を定める重要なステップです。特に公共工事では、発注者ごとに求められる内容や形式が異なることがあるため、事前の擦り合わせが重要になります。
協議内容は必ずメモを取り、後の施工計画書作成に反映させましょう。
協議が終わったら、テンプレートや雛形を準備します。
施工計画書のテンプレートは以下のような方法で入手できます。
テンプレートを使用する際は、そのまま流用するのではなく、現在の工事に合わせて適切にカスタマイズすることが重要です。特に安全対策や品質管理方法は、工事ごとに異なる部分ですので、注意して修正しましょう。
最後のステップは、実際に施工計画書を作成し提出することです。
作成の際は以下のポイントに注意します。
作成した施工計画書は、提出前に必ず社内でチェックを行いましょう。特に工事担当者や安全担当者など、複数の視点からの確認が重要です。
提出後、発注者から修正や追加資料を求められることもあります。その際は迅速に対応し、合意を得た上で工事を開始することが大切です。

施工計画書に記載すべき項目は、工事の種類や規模、発注者の要求によって異なりますが、基本的な記載項目があります。
これらの項目を適切に記載することで、発注者に認められる質の高い施工計画書を作成することができます。
施工計画書の具体的な記載項目やより詳しい作成方法については、「施工計画書の作り方|初心者でもわかる手順・記載項目・テンプレート活用法」をご参照ください。
こちらの記事では、初心者の方でも理解しやすいように、ステップごとの解説やテンプレートの活用方法を詳しく紹介しています。

施工計画書に関して、現場担当者や初めて作成する方からよく寄せられる質問にお答えします。
施工計画書は基本的に工事着工前に提出する必要があります。
提出期限は契約書や特記仕様書で確認してください。明記されていない場合は、発注者に直接確認しましょう。提出が遅れると工事着工が認められないこともあるため注意が必要です。
施工計画書は、一般的に現場代理人や監理技術者が作成します。
法的には建設業法で「主任技術者または監理技術者の職務」とされていますが、実務では工事規模に応じて適切な体制で作成されます。
施工計画書の作成時間は工事の規模や複雑さによって異なります。
過去の類似工事の施工計画書をテンプレートとして活用できれば、作成時間を短縮できます。現場調査や発注者との協議、社内での確認作業なども含めると、さらに時間が必要になることを考慮しましょう。
施工計画書は、建設工事を安全かつ効率的に進めるための重要な基本文書です。
本記事では、施工計画書の定義から必要性、法的根拠、作成手順、記載項目まで幅広く解説しました。施工計画書は単なる形式的な書類ではなく、工事の安全性・品質・効率性を確保するために欠かせないものです。
請負金額500万円以上の工事では法的に作成が義務付けられていますが、それ未満の工事でも自主的に作成することで、トラブルを未然に防ぎ、円滑な工事進行が可能になります。
弊社では、土木施工管理のプロフェッショナルが、お客様の工事に最適な施工計画書を作成いたします。法令に準拠し、かつ実務に即した実用的な施工計画書で、お客様の工事をサポートいたしますので、ぜひお気軽にご相談ください。
【お役立ち情報】
コメント