お急ぎの方はコチラ
受付時間:平日9:00 - 18:00
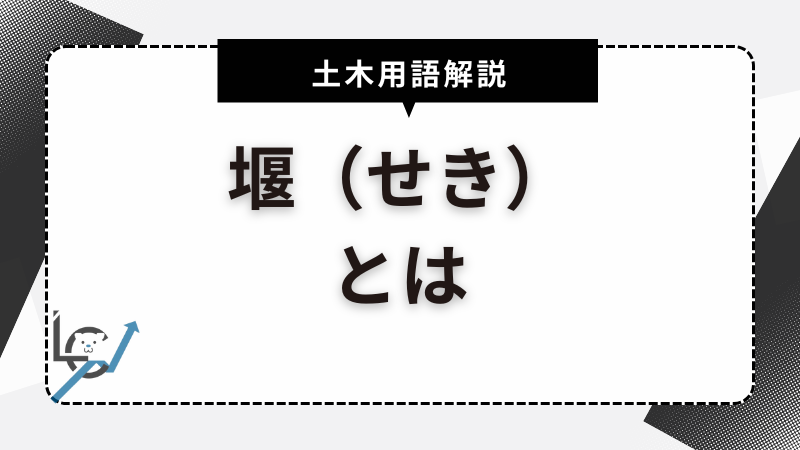
「川にある「堰(せき)」って何だろう?」
「堰とダムの違いがよくわからない」
このような疑問をお持ちではありませんか?
堰は、河川を横断して水位を調整する施設です。私たちの生活に必要な農業用水や飲料水を安定供給する重要な役割を担っています。
そこで、この記事では、堰について詳しく知りたい方へ向けて、基本的な定義から仕組み、ダムとの違い、種類や活用例まで幅広く解説します。「堰を切る」などの関連用語も紹介しますので、ぜひ最後までお読みください。

堰(せき)とは、河川を横断して設置される水利施設のことです。
川の流れをコントロールし、水位を調整することで、私たちの生活に必要な水を安定的に供給する重要な役割を担っています。
この章では、以下の2つのポイントから堰について解説します。
それぞれ詳しく見ていきましょう。
堰は「せき」と読みます。
漢字の「堰」は、土へんに「匽」と書き、水をせき止める構造物を表す文字です。なお、「い」や「いせき」という読み方もありますが、現代では「せき」が最も一般的な読み方となっています。
英語では主に「weir(ウィア)」と表記されます。これは比較的小規模な堰を指す言葉です。
一方、大規模な可動式の堰は「barrage(バラージ)」と呼ばれることもあります。海外の文献を読む際は、この2つの使い分けを理解しておくと便利です。
日本語では規模に関わらず「堰」という言葉を使いますが、英語圏では構造や規模によって使い分けられているのが特徴です。
堰とは、河川を横断して水の流れを調整する構造物のことです。
主な目的は、河川の水位を上昇させて、農業用水や工業用水として取水しやすくすることです。単に水をせき止めるだけでなく、必要な分だけ水を流す調整機能も持っています。
堰が設置される場所は、主に中流域から下流域にかけてです。上流のような急流では設置が困難なため、比較的流れが緩やかな場所が選ばれます。
また、堰は洪水時には水を安全に流下させる役割も担います。平常時は水位を上げて取水を容易にし、増水時は速やかに水を流すという、相反する機能を両立させているのです。
このように堰は、私たちの生活に欠かせない水資源を効率的に利用するための重要な施設なのです。

堰は河川の水を有効活用するための多機能な施設です。
この章では、堰の3つの重要な役割を解説します。
堰の基本的な役割は、河川の水位を上げて取水しやすくすることです。
水田や工場への取水口は、一定の高さに設置されています。堰がなければ水位が低すぎて、必要な水を取り込めません。
流量調整は、可動堰のゲート操作で行います。ゲートの開度を変えることで、下流への放流量をコントロールできるのです。
固定堰の場合は、水位が堰を越えると自動的に下流へ流れる仕組みになっています。
堰は異常気象時にも重要な役割を果たします。
洪水時はゲートを全開にして、水を速やかに流下させます。これにより上流の水位上昇を防ぎ、浸水被害を軽減します。
渇水時は逆にゲートを閉め気味にして、水位を維持します。河川流量が減っても、最低限の取水量を確保できるのです。
このように堰は、水量の変動に対応しながら安定的な水供給を実現しています。
堰の設置は河川生態系に影響を与えるため、様々な配慮が必要です。
最大の課題は魚の遡上阻害です。そのため現代の堰には「魚道」が設置され、アユやサケが上流へ移動できるようになっています。
また、堰の上流では土砂が堆積しやすく、下流では河床が削られる傾向があります。
最近は生態系への影響を最小限に抑える「多自然型」の堰づくりが進められています。

堰とダムはどちらも川の水を利用する施設ですが、明確な違いがあります。
この章では、堰とダムの違いを4つの観点から解説します。
ダムと堰の最大の違いは、水を貯めるか流すかという点です。
ダムは大量の水を貯水池に貯める施設です。洪水調節や発電、水道用水の確保など、長期的な水資源管理を目的としています。
一方、堰は水位を調整しながら流す施設です。必要な分だけ取水し、残りは下流へ流すという、短期的な水利用が主な目的となります。
つまり、ダムは「貯める」、堰は「調整して流す」という根本的な違いがあるのです。
法律上、ダムと堰は堤高(高さ)で区別されます。
河川管理施設等構造令では、堤高15m以上をダム、15m未満を堰と定義しています。この15mという数字が、両者を分ける明確な基準です。
| 施設 | 堤高 | 主な機能 |
|---|---|---|
| ダム | 15m以上 | 貯水・洪水調節 |
| 堰 | 15m未満 | 取水・水位調整 |
構造面でも、ダムは巨大なコンクリート構造物ですが、堰は比較的シンプルな構造となっています。
「砂防ダム」と呼ばれる施設の正式名称は「砂防堰堤」です。
砂防堰堤は土砂災害を防ぐための施設で、通常のダムとは目的が異なります。高さが15m以上でも「ダム」ではなく「堰堤」と呼ばれるのが特徴です。
これは河川法ではなく砂防法に基づく施設だからです。法律が違えば、同じような構造物でも名称が変わるという例です。
一般的には「砂防ダム」と呼ばれますが、正確には堰の仲間として扱われています。
現在の15m基準は、実は比較的新しいルールです。
旧河川法時代(1964年以前)に建設されたダムの中には、高さ15m未満のものも存在します。これらは現在の基準では堰に分類されるはずですが、歴史的経緯から「ダム」と呼ばれ続けています。
例えば、大正時代に建設された農業用ダムには、高さ10m程度のものもあります。
このように、古い施設については現在の分類基準が必ずしも当てはまらないケースがあることを知っておくとよいでしょう。

堰には構造や用途によって様々な種類があります。
この章では、堰の分類と実際の活用例を解説します。 ・構造による3つの分類 ・用途別の具体的な活用事例
堰は構造によって大きく3つに分類されます。
固定堰は、コンクリートや石で作られた動かない堰です。構造がシンプルで維持管理が容易ですが、水位調整の柔軟性は低くなります。
可動堰は、ゲートを上下させて水位を調整できる堰です。洪水時にはゲートを開けて水を流し、平常時は閉めて水位を保つことができます。
仮堰は、工事などで一時的に設置される堰です。土のうや鋼矢板で作られ、工事終了後は撤去されます。
| 種類 | 特徴 | メリット | デメリット |
|---|---|---|---|
| 固定堰 | 動かない構造 | 維持管理が簡単 | 水位調整が困難 |
| 可動堰 | ゲートで調整可能 | 柔軟な水位管理 | 維持費が高い |
| 仮堰 | 一時的な設置 | 設置・撤去が容易 | 耐久性が低い |
現在は洪水対策の観点から、新設される堰の多くが可動堰となっています。
堰は用途によって設計や運用方法が異なります。
農業用堰の代表例は、利根川の「利根大堰」です。埼玉県の農業用水を供給する重要な施設で、約15万ヘクタールの農地に水を送っています。
工業用では、愛知県の「明治用水頭首工」が有名です。トヨタ自動車をはじめとする工場地帯への工業用水供給を担っています。
都市河川では、東京の「調布取水堰」があります。多摩川から取水し、都民の飲料水として利用されているのです。
最近では多目的堰も増えています。一つの堰で農業用水、工業用水、上水道を同時に取水する効率的な運用が行われています。
このように堰は、地域の特性や需要に応じて様々な形で活用されているのです。

堰に関する言葉には、日常会話で使われる慣用句や専門用語があります。
この章では、堰にまつわる表現について解説します。 ・慣用句「堰を切る」の意味 ・混同しやすい専門用語
「堰を切る」は、感情などが一気にあふれ出す様子を表す慣用句です。
「堰を切ったように泣く」「堰を切ったように話し始める」など、抑えていたものが一気に出てくる場面で使われます。
この表現の由来は、実際の堰の仕組みにあります。堰で水をせき止めていた状態から、堰を開放すると水が勢いよく流れ出すことからきています。
つまり、今まで我慢していた感情が、何かのきっかけで抑えきれなくなる様子を、堰の水に例えているのです。
日本語特有の表現で、英語には直接対応する慣用句はありません。
堰に関連する専門用語は、似た漢字が使われるため混同しやすいものがあります。
「堰堤(えんてい)」は、堰とダムの総称として使われる言葉です。特に「砂防堰堤」のように、土砂を止める施設の名称によく使われます。
「堰止湖(せきとめこ)」は、土砂崩れなどで川がせき止められてできた天然の湖です。人工的な堰とは関係なく、自然現象でできた湖を指します。
| 用語 | 読み方 | 意味 |
| 堰堤 | えんてい | 堰とダムの総称 |
| 堰止湖 | せきとめこ | 自然にできた湖 |
| 頭首工 | とうしゅこう | 農業用の取水堰 |
「頭首工(とうしゅこう)」も堰の一種ですが、特に農業用水を取水する施設を指す専門用語です。
これらの用語を正しく理解することで、河川施設についての理解が深まります。
堰(せき)は、河川を横断して水位を調整し、私たちの生活に必要な水を供給する重要な施設です。
堤高15mを境にダムと区別され、ダムが「貯める」のに対し、堰は「調整して流す」という役割を担っています。
固定堰や可動堰など様々な種類があり、農業用水、工業用水、上水道など、地域のニーズに応じて活用されています。
普段何気なく見ている川にも、多くの堰が設置されています。堰の役割を理解すると、水がどのように管理され、私たちの元に届いているかが見えてきます。
次に川を訪れた際は、ぜひ堰を探してみてください。きっと今までとは違った川の姿が見えてくるはずです。
【お役立ち情報】
コメント