お急ぎの方はコチラ
受付時間:平日9:00 - 18:00
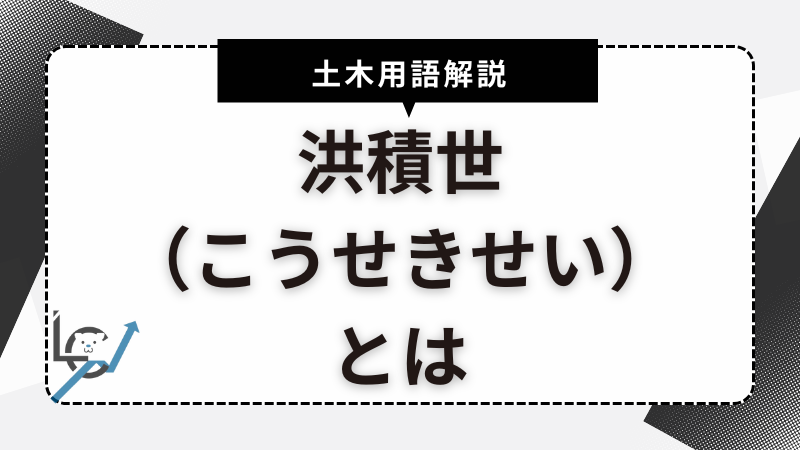
洪積世(こうせきせい)とは、地質時代区分の一つであり、約258万年前から1万年前までの期間を指します。更新世とも呼ばれ、第四紀の前半を占める時代です。氷河期と間氷期が繰り返し訪れた時期であり、マンモスなどの巨大哺乳類が生息していました。
洪積世(こうせきせい)は地質学的には「更新世」とも呼ばれ、第四紀を構成する2つの時代区分のうちの1つです。約258万年前に始まり、約1万年前に終わったとされています。
この時代の最大の特徴は、氷河期と間氷期が繰り返し訪れたことです。少なくとも4回の大きな氷河期があり、その間には比較的温暖な間氷期が存在しました。これらの気候変動は地球全体の環境に大きな影響を与えました。
洪積世には海水面の上下動が激しく、最大で100メートル以上も変動したことがあります。氷河期には海水が氷として陸地に閉じ込められるため海面が下がり、間氷期には氷が溶けて海面が上昇しました。
地層学的には、洪積層と呼ばれる特徴的な堆積物が形成されました。これらは主に河川や風、氷河などによって運ばれた砂や礫、粘土などから成り、現在の台地や段丘の基盤となっています。
人類の歴史においても重要な時代です。ホモ・エレクトスからホモ・サピエンスへの進化が進み、原人から新人への移行が完了しました。また、人類が道具を使い始め、火の使用を覚えたのもこの時期とされています。
洪積世(こうせきせい)と沖積世(ちゅうせきせい)は、地質時代の区分として重要な2つの時代です。
洪積世は約258万年前から1万年前までの長い期間を指し、更新世とも呼ばれます。一方、沖積世は約1万年前から現在までの比較的短い期間で、完新世とも呼ばれています。
両者の最も大きな違いは気候条件です。洪積世は氷河期と間氷期が繰り返し訪れた不安定な気候が特徴でしたが、沖積世は比較的安定した温暖な気候が続いています。
地層の特性も異なります。洪積層は一般的に固く締まっており、建築物の基礎として優れた支持力を持っています。一方、沖積層は柔らかく、水を含みやすい特性があり、地震時には液状化しやすい傾向があります。
また、生物相にも大きな違いがあります。洪積世にはマンモスなどの巨大哺乳類が生息していましたが、沖積世になるとそれらの多くは絶滅し、現在の生物相へと変化しました。
洪積世(こうせきせい)には、現在では見られない特徴的な生物が多数生息していました。
代表的なものには以下があります。
これらの生物の多くは洪積世の終わり頃に絶滅し、現在では化石としてのみ見ることができます。絶滅の原因については、気候変動や人類の狩猟活動など、様々な説が提唱されています。
【お役立ち情報】
コメント