お急ぎの方はコチラ
受付時間:平日9:00 - 18:00
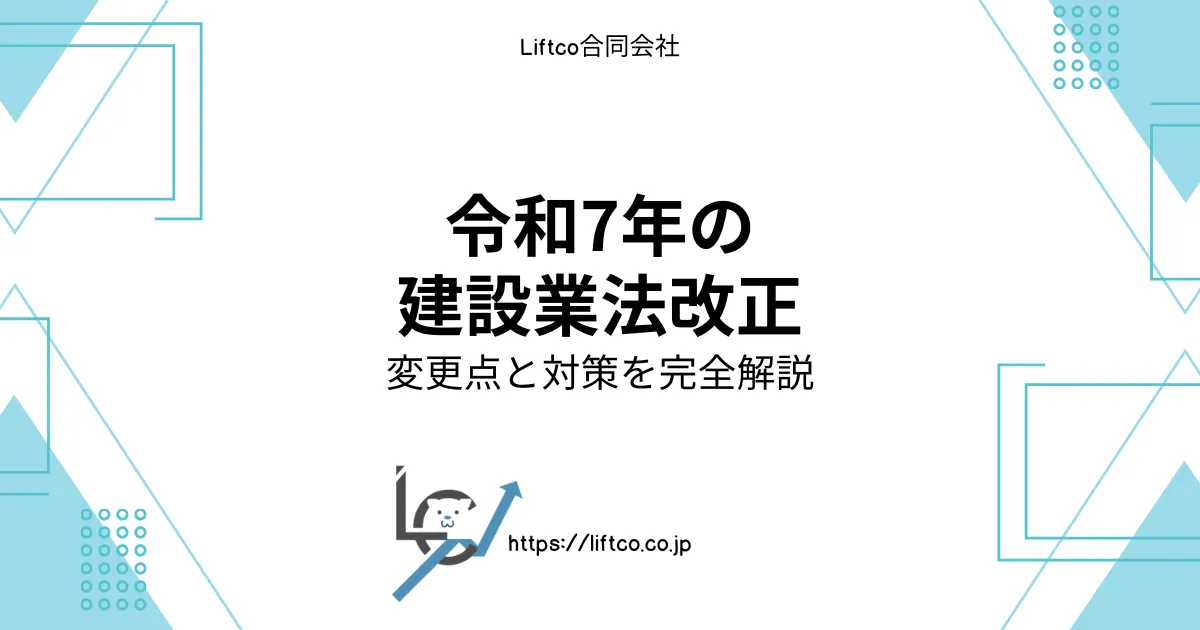
「建設業法改正 令和7年はいつから始まるの?」
「技術者配置や許可制度はどう変わるのかわからない」
「自分の会社は何を準備すればいいか知りたい!」
このようなお悩みはありませんか?
建設業法改正 令和7年は、建設業界の労働環境改善と適正化を目的とした重要な法改正です。正確な情報を把握することで、スムーズな対応と違反リスクの回避が可能です。
そこで、この記事では、建設業に関わる方へ向けて施行日や変更内容、必要な準備について解説します。法改正への対策や準備の参考として、ぜひ最後までお読みください。

令和7年の建設業法改正は、建設業界で働く人の待遇改善と業界の健全化を目的とした法律の見直しです。
この改正には大きく3つのポイントがあります。
国土交通省は建設従事者が適正な賃金を受け取れるよう、労務費の基準を明確に示します。また、監理技術者の配置が必要な工事の金額要件も変更されます。これらの変更により、建設業界全体がより適正で健全な運営を求められるようになります。
参考:国土交通省|建設業法・入契法改正(令和6年法律第49号)について
建設業法改正 令和7年は、2025年12月から全面施行される予定です。
国土交通省は段階的な導入を計画しており、一部の制度については2027年度から試験運用が始まります。例えば、労働者が適正な賃金を受け取っていないと感じた場合の通報制度などが該当します。
建設業に関わる企業は、2025年12月までに新しいルールに対応した体制を整える必要があります。準備期間を考慮して、早めの対策が重要となるでしょう。法改正の詳細な内容については、国土交通省から順次発表される予定です。
参考:国土交通省|建設業法・入契法改正(令和6年法律第49号)について

令和7年の建設業法改正では、建設業界の根幹に関わる重要な変更が行われます。
主な変更分野は以下の3つです。
これらの変更により、建設業界全体がより適正で健全な運営を求められるようになります。労働者の処遇改善、業界の透明性向上、適正な競争環境の確保が主な目的です。2025年12月から段階的に施行される予定のため、建設業に関わる企業は早急な準備が必要となります。
参考資料: 国土交通省「建設業法・入契法改正(令和6年法律第49号)について」
建設業法改正 令和7年では、労働者の賃金に関する制度が大幅に見直されます。
これまで曖昧だった労務費の基準が明確化され、適正な賃金支払いが法的に義務付けられます。国土交通省が建設従事者の労務費基準を示し、この基準を下回る賃金は法律違反となります。
とび職や鉄筋工などの職種ごとに適正な賃金水準が設定されます。建設業者はこの基準に従って労働者に適切な賃金を支払う責任が明確になります。基準に従わない場合は指導や処分の対象となる可能性があります。
参考資料: 国土交通省「建設業法・入契法改正(令和6年法律第49号)について」
労働者が適正な賃金を受け取っていないと感じた場合の通報制度が2027年度から試験運用されます。この制度により、建設業で働く人は賃金に問題があると思った場合、国の機関に直接通報できるようになります。通報を受けた国土交通省は調査を実施し、問題が確認されれば適切な処分を行います。
資材価格の急激な変動に対する対応方法が明確化されます。契約書には資材高騰時の価格変更方法を記載することが義務付けられ、価格調整協議がスムーズに行えるようになります。これにより労務費へのしわ寄せを防ぐ仕組みが整備されます。
参考資料: 国土交通省「建設業法・入契法改正(令和6年法律第49号)について」
令和7年の建設業法改正では、監理技術者の配置に関するルールが変更されます。
主な変更点は配置が必要な工事の金額基準が引き上げられることです。現在よりも高額な工事でのみ、専任の監理技術者を配置することが義務付けられる予定です。
| 項目 | 現行 | 改正後 |
|---|---|---|
| 特定建設業許可を要する下請代金額 | 4,500万円 | 5,000万円 |
| 施工体制台帳等の作成を要する下請代金額 | 4,500万円 | 5,000万円 |
| 監理技術者の専任が必要な工事金額 | 4,000万円 | 4,500万円 |
この変更により、中小規模の工事では監理技術者の専任配置が不要になる場合があります。一方で、大規模工事では引き続き厳格な技術者配置が求められます。
参考資料: 国土交通省「建設業の各種金額要件や技術検定の受検手数料を見直します」
監理技術者の配置が必要な工事は、元請として受注する工事のうち、一定金額以上の下請契約を含む工事です。土木工事や建築工事などの主要な建設工事が該当し、改正後も基本的な対象工事の種類に大きな変更はありません。ただし金額要件の変更により、対象となる工事の範囲が調整されます。
参考資料: 国土交通省「建設業法令遵守ガイドライン」
建設業法改正 令和7年では、特定建設業許可の取得要件にも変更が加えられます。
許可取得の条件が一部見直され、技術者の専任配置要件についてより厳格な基準が設けられる予定です。また、元請業者と下請業者の関係についても新たなルールが整備されます。
技術者の専任配置要件について、これまでよりも厳格な基準が設けられます。監理技術者や主任技術者の配置に関する条件が明確化され、適切な技術者を継続的に確保する体制が求められるようになります。許可を維持するためには、新しい基準に適合する必要があります。
参考資料: 国土交通省「建設業の各種金額要件や技術検定の受検手数料を見直します」
元請業者は下請業者に対して、適正な労務費を含む契約金額を提示する義務が強化されます。安すぎる見積りでの下請契約は法的な問題となる可能性が高くなります。下請業者側も、不当に安い契約を受け入れることがないよう注意が必要です。契約書の記載内容についても、これまで以上に詳細な記録が求められるようになります。
参考資料: 国土交通省「建設業法・入契法改正(令和6年法律第49号)について」

令和7年の建設業法改正に違反した場合、従来よりも厳しい処罰が科されることになります。
違反の程度に応じて下記の処罰が科されます。
特に労務費基準に関する違反については、労働者の生活に直結するため厳格に処分されます。違反が発覚した場合の影響は企業経営に深刻なダメージを与える可能性があります。
それぞれ詳しく説明していきます。
建設業法改正 令和7年で新設される労務費基準に違反した場合、段階的な処罰が科されます。
初回の違反では指導処分が行われ、改善計画の提出が求められます。改善が見られない場合や再違反の場合は、営業停止処分となります。営業停止期間は違反の程度により1ヶ月から6ヶ月程度です。
悪質な違反や繰り返し違反を行った場合は、建設業許可の取り消し処分が科されます。許可を取り消されると、建設業を営むことができなくなり、事実上の廃業を余儀なくされます。また、処分を受けた役員は一定期間、他の建設業者の役員にもなれません。
参考:国土交通省|建設業法・入契法改正(令和6年法律第49号)について
令和7年の建設業法改正により、違反発覚から処分までの流れも明確化されます。
通報制度や定期監査により違反が発覚した場合、国土交通省は速やかに調査を開始します。調査期間は通常1〜3ヶ月程度で、この間に事情聴取や資料提出が求められます。
調査の結果、違反が確認されると処分の内容が決定されます。処分決定後は官報での公表や建設業者名簿への記載が行われ、取引先や金融機関にも影響が及びます。処分期間中は新規契約の獲得が困難になり、既存契約にも影響する可能性があります。早期の改善対応が企業存続の鍵となるでしょう。
参考:国土交通省|建設業法違反の通報窓口(駆け込みホットライン)

令和7年の建設業法改正に向けて、建設業者が今から準備すべき大切なことがあります。
2025年12月の開始まで時間は限られています。
準備が必要な項目は主に2つです。
これらの準備をしないと、新しいルールが始まってから困ることになります。また、知らないうちにルール違反をしてしまう危険性もあります。早めに準備を始めることが大切です。
建設業法改正 令和7年に備えて、技術者の配置計画を見直す必要があります。
お金の基準が変わるので、技術者が必要な工事と不要な工事が変わります。自分の会社がどんな工事をするかを整理して、どの工事に技術者が必要かを確認してください。
また、技術者が足りない場合の対策も考えましょう。資格を持つ人を新しく雇ったり、今いる社員に資格を取ってもらうことが必要です。技術者がいないと工事を受けられなくなるので、計画的に人を確保することが重要です。
令和7年の建設業法改正に向けて、契約書や書類の見直しも必要です。
特に人件費に関する内容は、新しい基準に合わせて変更が必要です。下請け会社との契約では、きちんとした人件費を含んだ金額であることをはっきり書く必要があります。
また、技術者に関する書類も新しくしてください。工事現場にいる技術者の資格や役割を正確に記録し、国から求められたときにすぐ出せるようにしておきましょう。書類に間違いがあると問題になるので、詳しい人と相談しながら確実に準備することが大切です。

令和7年の建設業法改正について正確な情報を集める方法は主に2つあります。
法律の改正は複雑で、間違った情報に基づいて準備すると大きな問題になります。
インターネット上には様々な情報がありますが、すべてが正確とは限りません。信頼できる情報源から最新の内容を入手することが重要です。
また、自分だけで判断せず、専門家の意見を聞くことも大切です。
建設業法改正 令和7年の正確な情報は、国土交通省の公式発表で確認できます。
国土交通省のホームページでは、建設業法改正に関する最新情報が公開されています。また、審議会や検討会の会議資料も閲覧可能です。これらの資料には改正の詳細な内容や実施スケジュールが記載されています。
ただし、国の資料は専門用語が多く、理解が困難な場合があります。法律の条文や技術的な説明が中心で、実際の業務にどう影響するかがわかりにくいのが現状です。そのため、国の情報を基にしながらも、わかりやすく解説してくれる専門家の意見を併せて確認することが重要です。
令和7年の建設業法改正について、専門家に相談することも重要な情報収集方法です。
建設業法に詳しい行政書士や弁護士に相談すれば、自分の会社の状況に合わせたアドバイスを受けられます。また、建設業協会や商工会議所でも相談窓口を設けている場合があります。
国土交通省の情報ではわかりづらい箇所が多いため、弊社のサイトのようにわかりやすく解説する専門家も活用しましょう。複雑な法律用語を日常的な言葉で説明し、具体的な対応策まで提示してくれる専門サイトは、忙しい建設業者にとって貴重な情報源です。弊社では建設業に関する最新情報を随時更新し、実務に役立つ解説を提供しています。
建設業法改正 令和7年は2025年12月から全面施行され、建設業界に大きな変化をもたらします。
主な変更点は以下の通りです。
これらの変更により、建設業者には適正な賃金支払いと法令遵守がこれまで以上に求められます。違反した場合は営業停止や許可取り消しといった重い処分が科される可能性があります。
施行まで残り時間は限られているため、技術者配置の見直しや契約書の更新など、早急な準備が必要です。
国土交通省の公式情報を確認しながら、専門家のサポートも活用して確実な対応を進めましょう。
【お役立ち情報】
コメント