お急ぎの方はコチラ
受付時間:平日9:00 - 18:00
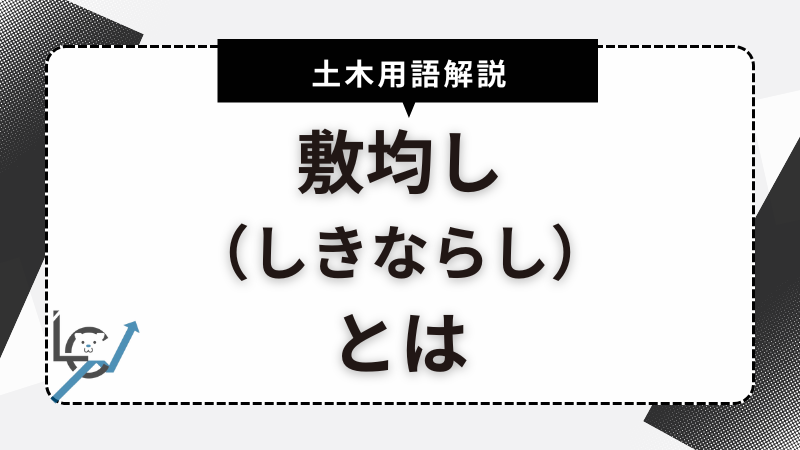
敷均し(しきならし)とは、土木工事や造成工事において、地面に敷きならされた土砂や砕石などを均一な厚さと高さに整える作業を指します。
この作業の目的は、後に続く転圧や構造物の設置を正確に行うための基礎を整えることにあります。
例えば、砕石を均一な厚みで敷きならすことで、沈下や不陸が起こりにくくなります。
敷均しに使用される主な機械には、ブルドーザーやグレーダー、マシンコントロール技術を搭載したバックホウなどがあります。
見た目には単純な作業に見えるかもしれませんが、仕上がり精度が工事全体の品質に大きく影響するため、非常に重要な工程といえます。
敷均しと整地は、どちらも地面を整える作業ですが、その目的や工程にははっきりとした違いがあります。
敷均しは、砕石や土砂を均一に広げて厚さや高さを調整する工程で、構造物の正確な設置を支えるために行います。
一方で整地は、地面全体を平らにして外観や作業性を整える工程で、最終的な仕上げのような役割を担います。
以下の表に両者の違いをまとめました。
| 項目 | 敷均し(しきならし) | 整地(せいち) |
|---|---|---|
| 主な目的 | 厚さ・高さを均一に調整し、施工精度を確保する | 見た目や作業性を整え、地面を使いやすくする |
| 作業タイミング | 基礎施工の前工程 | 工事終盤、仕上げとして行われることが多い |
| 使用材料 | 砕石、土砂など | 表面土、芝、舗装前の土など |
| 使用機械 | グレーダー、ブルドーザー、バックホウなど | 整地用ローラー、整地プレートなど |
| 精度の重要性 | 高い(数センチ単位の精度が求められる) | 中程度(使用目的に応じて調整) |
このように、両者は似て非なる作業です。現場の進行に応じて適切に使い分けることが、品質の高い施工に繋がります。
敷均しは、構造物の基礎となる砕石層を「均一に・正確に」整える作業であり、建物の安定性に直結する重要な工程です。
例えば、建物の基礎砕石を敷く際に厚さにムラがあると、その上に設置するコンクリート基礎が部分的に沈んだり傾いたりする恐れがあります。
最悪の場合、建物全体が傾いて扉や窓が正常に開閉できなくなったり、基礎にひび割れが発生して雨水が侵入するなど、重大な構造不良につながる可能性もあります。
一方で、精度の高い敷均しが行われていれば、転圧も効率よく進み、強固で水平な基礎が完成します。
このように、敷均しは見えない部分の作業でありながら、建物の寿命や安全性を左右する非常に重要な役割を担っています。
敷均し作業では、精度の高い仕上がりを確保するために、国土交通省が定める出来形管理基準を満たすことが求められます。
基礎砕石においては、厚さや幅のばらつきを抑え、設計値に近づける必要があります。
下表は、砕石基礎工における代表的な出来形管理の基準を示したものです。
| 管理項目 | 設計値に対する基準 | 測定頻度 |
|---|---|---|
| 幅(w) | 設計値以上 | 施工延長40mごとに1か所(25m測点間隔の場合は50mごと)、 または延長40m以下のものは施工箇所につき2か所 |
| 厚さ(t1) | -30mm | |
| 厚さ(t2) | -30mm | |
| 延長(L) | 構造物の規格値による |
参考:国土交通省|土木共通仕様書
例えば、厚さが設計より30mm以上薄い場合は不適合と判定され、再施工が必要となる可能性があります。
そのため、敷均しの際はレーザーレベルや丁張りを使い、常に設計値を意識して
【お役立ち情報】
コメント