お急ぎの方はコチラ
受付時間:平日9:00 - 18:00
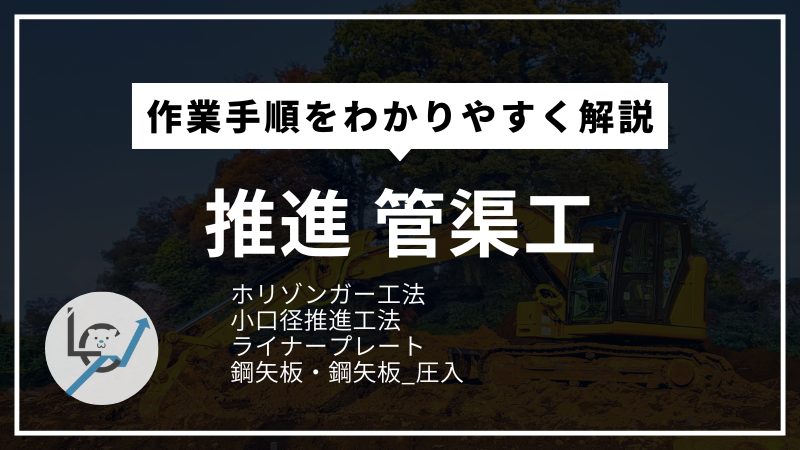
下水道などの重要な構成要素である管渠(かんきょ)の工事方法の1つに「推進工法」があります。
管渠とは何か、その概要や種類については、こちらの記事で詳しく解説していますので、あわせてご覧ください。
ホリゾンガー工法は、高耐荷力方式のオーガー推進工法の一種で、一工程で掘削と推進を同時に行う工法です。この工法は特に中小口径の管渠推進に適しており、市街地における効率的な管渠敷設を可能にします。
以下に、この工法の詳細な作業手順を解説します。
ホリゾンガー工法による管渠推進工事は、専用機械の搬入から始まります。搬入時には周辺環境を考慮し、通行車両や歩行者の安全を確保するため、必要に応じて交通誘導員を配置します。
搬入作業で使用するワイヤーロープやフックなどの安全金具は事前に点検し、玉掛け作業は有資格者が担当します。クレーンは安定した場所に設置し、安全な作業環境を整えます。
推進機本体とフレームを立坑内に吊り降ろす際は、バランスを考慮してワイヤーを取り付け、水平を保ちながら作業します。立坑内に設置後、専用ジャッキを用いてレール中心を埋設計画線に合わせ、前後左右の位置を決定します。
レベルジャッキを使用してレール面が設計勾配になるように調整します。管径によってレール高さは異なるため、施工計画に基づいた正確な調整が必要です。本体を設定位置に据え付けたら、フレームを仮設材としっかり固定し、推進作業中の位置ずれを防止します。
支圧壁は推進力を受け止める重要な構造物です。推進方向に対して直角かつ平面になるように設置し、高い推進力が加わっても破壊や変形が生じないよう堅固に構築します。支圧壁が推進方向に対して直角でない場合は、スペーサーなどを用いて調整します。
ホリゾンガー工法では、先導管(掘削部)の組立と調整が精度確保の鍵となります。通常3分割式の先導管は、ボルトで一体化します。組立前に先端ヘッド、スクリュー、ケーシングの状態を入念に確認します。
本体への接続後、先導管の高さと方向をレベルと測量機器で調整します。特にトランシットは推進勾配に合わせて固定し、視準線がターゲットの基準線と一致するよう設定します。推進管の計画線とターゲットの中心線が一致するように調整することで、高精度な推進が可能になります。
先導管の各種システム(方向修正機能、ターゲット照明、注水システム)の作動確認は、推進精度に直結するため入念に行います。
鏡切り(立坑壁の切断)は、地盤の安定性を確認してから実施します。確認孔を開けて地盤状態を確認した後、下部から順に切断を進めます。切断サイズは先導管が余裕をもって通過できるよう、管径に応じた適切な大きさにします。
鋼矢板の場合は、特にセクション部分の切断に注意し、切断後は状態を十分確認します。管径によって必要な切断長は異なるため、施工計画に基づいて正確に作業を行います。
坑口部は推進精度の起点となる重要な部分です。推進管計画線の中心と推進管の中心高さを正確に合わせ、堅固に設置します。坑口と仮設材(鋼矢板、ライナープレートなど)の間は隙間なく鋼板で埋め、溶接で固定します。
推進方向が仮設材に対して斜めになる場合は特に注意し、推進方向に対して坑口が直角になるよう調整します。管径ごとに最適な坑口寸法を選定することも重要です。
管の据付作業は安全と精度を重視します。まず吊り降ろし用ワイヤーを点検し、管が水平になるように吊り上げます。横ブレ防止のため補助ロープを使用し、立坑壁との接触を避けながら慎重に吊り降ろします。
オーガースクリューの接続では、羽根の連続性を確保するよう位置を合わせます。ケーシングは均等にボルトを締め付け、曲がりを防止します。方向修正用ホースや電気ケーブルの接続は接続ミスがないよう確認しながら行い、管内での損傷を防ぐよう適切に配置します。
管の接続前には接合部を清掃し、ゴム輪と接合部に専用滑剤を十分塗布します。接続時にはゴム輪の状態を確認しながら作業し、水密性を確保します。
ホリゾンガー工法での管推進は、カラー(受口)を後部にして行います。オペレーターは推進力、オーガー電流値、排土状況を常に監視し、オーガーの回転数、推進速度、注水量を地盤条件に応じて調整します。
測量担当者は先導管の位置を継続的に確認し、ターゲットの読み取り値から進行方向を予測します。計画線からのずれを早期に発見し、方向修正を適時行うことで高精度な推進を実現します。
方向修正は立坑内のトランシットによるターゲット観測に基づいて行います。計画線との誤差を確認し、先導管の油圧シリンダーを操作して上下左右の方向を調整します。位置検出はトランシットによる目視またはレーザー方式で行い、精度の高い管路線形を維持します。
到達立坑での鏡切りも発進立坑と同様に、地盤状態を確認しながら慎重に行います。先導管が正確に到達できるよう、計算された位置を適切なサイズで切断します。
先導管が到達立坑に到達したら、まずケーシング内の残土を発進側に排出します。オーガーヘッドは押出金具を使用して前方に押し出し、継手ピンを抜いて分離します。
先導管は到達立坑内で継手部を分解し、油圧ホースと電気ケーブルを切り離してから回収します。バックアップパイプも段階的に接続部を解体し、部分ごとに撤去します。スクリューとケーシングは発進坑へ引き抜いて回収します。
オーガースクリューとケーシングパイプの回収には引抜き金具と滑車を使用し、クレーンで慎重に引き上げます。ケーシング回収時には油圧ホースや電気ケーブルも同時に回収するため、これらを損傷しないよう細心の注意を払います。
工事完了後は機器の解体作業に移ります。油圧ホースや電気ケーブルを撤去し、支圧壁やスペーサーを解体します。安全金具を点検した上で、有資格者の監督のもと推進機の各部を解体して撤去します。
搬出時も搬入時と同様に安全を最優先し、周辺環境に配慮します。通行車両や歩行者の安全確保のため、必要に応じて交通誘導員を配置し、機材を安全に搬出します。
小口径推進工法(低耐荷力管推進工法)は、主に口径150mm~300mm程度の小口径管を地中に推進する工法です。この工法では、塩化ビニル管などの比較的耐荷力の低い管を使用し、効率的に管渠を敷設します。このセクションでは、小口径推進工法の詳細な作業手順を解説します。
小口径推進工事の最初のステップは、専用機械の搬入です。搬入前に現場状況を十分に確認し、通行車両や歩行者に支障が出ないようクレーンや運搬車の配置を計画します。必要に応じて交通誘導員を配置し、安全確保に努めます。
搬入作業で使用するワイヤーロープやフックなどの安全金具は事前に点検します。玉掛け作業は資格を持った作業員が担当し、クレーンは平坦で堅固な場所に設置して安全を確保します。
推進機本体とフレームを立坑内に吊り降ろす際は、所定の位置にワイヤーを取り付け、水平を保ちながら慎重に作業します。立坑内に設置後、付属のジャッキを使用してレールの中心を埋設計画線に合わせ、前後左右の位置を正確に決定します。
レベルジャッキを使って、レール面が設計勾配になるように調整します。小口径推進では管径別に適切なレール高さがあり、φ150mmからφ300mmまでの各サイズに応じた調整が必要です。
本体を設定位置に据え付けたら、フレームの前後左右を仮設材としっかり固定し、推進作業中の機械のズレやブレを防止します。
支圧壁は推進機からの力を地盤に伝える重要な構造物です。推進方向に対して直角かつ平面になるように設置し、土質変化などによる異常な推進力が加わっても破壊や変形が生じないよう堅固に構築します。
支圧壁が推進方向に対して直角でない場合は、スペーサーなどを用いて調整し、推進力が偏らないようにします。小口径推進では推進力は比較的小さいですが、支圧壁の設計と施工は精度確保のために重要です。
小口径推進工法でも先導管(掘削部)の組立と調整は精度を左右する重要な工程です。一般的に3分割式の先導管をボルトで一体化し、使用前に先端ヘッド、スクリュー、ケーシングの状態を入念に確認します。
先端ケーシングの組み込み時には、ターゲット、油圧ホース、電気ケーブルの配置と接続に十分注意します。本体に接続完了後、先導管先端の前後をレベルで測定し、設計高さに調整します。
トランシットを推進勾配に合わせて固定し、視準線がターゲットの基準線と一致するように設定します。左右方向は推進管計画線とターゲット中心線が一致するよう調整します。
先導管の油圧ホースと電気ケーブルを本機に接続し、方向修正機能、ターゲット照明、注水システムの作動確認を行います。これらの調整と確認が精度の高い推進を実現するための基盤となります。
鏡切り(立坑壁の切断)は、地盤の安定性を確認してから実施します。鏡切り前に確認孔を開け、地盤が自立していることを確認することで、切羽の崩壊や湧水を防止します。
切断は下部から順に行い、先導管が余裕を持って貫通できるサイズにします。鋼矢板の場合は特にセクション部分を丁寧に切断し、切断後は状態を確認します。
小口径推進では管径によって切断長が異なり、例えばφ150mmの場合はライナープレートで約1.0m、鋼矢板で約2.0mの切断長が必要です。立坑の仮設工法に応じた適切な切断サイズを確保します。
坑口は推進管の発進部を固定し、方向を定める重要な設備です。推進管計画線の中心と推進管の中心高さを正確に測量して合わせ、堅固に設置します。
坑口と仮設材(鋼矢板、ライナープレートなど)の間は、形状に合わせて鋼板を加工し溶接します。仮設材に対して推進方向が斜めになる場合は特に注意し、推進方向に対して坑口が直角になるよう調整します。
小口径推進では管径ごとに最適な坑口寸法があり、各部材のサイズ(フランジ外径・内径、リング板厚など)が規格化されています。適切な坑口を選定し、正確に設置することで、推進の初期精度を確保します。
管の据付は安全と精度を重視して行います。まず吊り降ろし用ワイヤーを点検し、管が水平になるように吊り上げます。横ブレ防止のため補助ロープを使用し、立坑壁との接触を避けながら慎重に吊り降ろします。
オーガースクリューの接続では、羽根の連続性を確保するよう位置を合わせます。ケーシングの接続はボルトを均等に締め付け、曲がりを防止します。
方向修正用ホースや照明ケーブルの接続は、接続ミスがないよう確認しながら行い、管内での損傷を防ぐよう適切に配置します。
小口径推進では使用する管種に応じた接合方法があります。SUSカラータイプでは管接合部を清掃し、接合部とゴム輪に塩ビ管用滑剤を塗布して接続します。接着カラータイプでは接合部に塩ビ管用接着剤を塗布し、所定の位置まで差し込みます。どちらの場合も水密性と強度を確保するために正確な接続作業が求められます。
管の推進は、カラー(接続部)を後部にして行います。推進機のオペレーターは推進力、オーガー電流値、排土状況を常に監視し、地盤条件に応じてオーガーの回転数、推進速度、注水量を調整します。
測量担当者は先導管の位置を継続的に確認し、ターゲットの読み取り値から先導管の移動傾向を分析します。計画線からのずれを早期に発見し、方向修正を適時行うことで高精度な推進を実現します。
方向修正は立坑内に設置したトランシット(セオドライト)を使用して行います。先導管内のターゲットを観測し、計画管路との誤差を確認します。基準線が常に一致するよう、先導管に内蔵された修正シリンダーを操作して方向を調整します。
小口径推進では、上下・左右方向の修正能力が特に重要です。修正装置は刃口に組み込まれた油圧シリンダーと立坑内の操作盤、それらを接続する油圧ホースで構成されています。位置検出はトランシットによる目視方式またはレーザー方式を用い、立坑内の基準位置からのズレを継続的に確認します。
到達立坑での鏡切りも発進立坑と同様の手順で行います。地盤状態を確認し、先導管が正確に到達できるよう適切なサイズで切断します。
先導管が到達立坑に到達したら、まずケーシングパイプ内の残土を発進坑側に排出します。オーガーヘッドは押出金具を使用して前方に押し出し、継手ピンを抜いて分離します。
先導管は到達立坑内で継手部を分解し、油圧ホースと電気ケーブルを切り離してから回収します。バックアップパイプも段階的に接続部を解体し、部分ごとに撤去します。スクリューとケーシングは発進坑へ引き抜いて回収します。
オーガースクリューとケーシングパイプの回収には引抜き金具と滑車を使用し、クレーンで慎重に引き上げます。ケーシング回収時には油圧ホースや電気ケーブルも同時に回収するため、これらを損傷しないよう細心の注意を払います。
工事完了後は機器の解体作業に移ります。油圧ホースや電気ケーブルを撤去し、支圧壁やスペーサーを解体します。安全金具を点検した上で、有資格者の監督のもと推進機の各部を解体して撤去します。
搬出時も搬入時と同様に安全を最優先し、周辺環境に配慮します。通行車両や歩行者の安全確保のため、必要に応じて交通誘導員を配置し、機材を安全に搬出します。
ライナープレート工法は、比較的小規模な立坑を構築する際に用いられる工法です。鋼製の曲板(ライナープレート)を組み合わせて円形や楕円形の立坑を構築します。地盤条件に応じて切梁や腹起しを設置することで、安全な作業空間を確保します。
立坑築造の最初のステップは、受桁の設置です。バックホウを使用して立坑予定箇所を水平に整地します。レベル(水準器)で高さと水平を確認しながら、所定の位置に受桁としてH鋼(H300)を井桁状に設置します。
受桁は立坑上部の荷重を支える重要な部材であり、正確な位置と水平度の確保が必要です。地盤の状態に応じて必要な補強を行うこともあります。
受桁設置後、立坑の掘削作業に入ります。まずライナープレート1段分(約50~60cm)の深さまで掘削します。掘削深さが5m程度までは通常のバックホウを使用し、それ以上の深さでは油圧クラムシェルなどの専用機械を使用します。
掘削した土砂はダンプトラックに積み込み、指定の仮置場に運搬します。掘削作業中は安全確保のため、開口部周囲に単管パイプなどで手すりを設置します。
掘削時には湧水や土質の変化に注意し、床掘りは偏りなく平均して掘り下げます。受桁に吊り金具を取り付け、1段目のライナープレートを高さを合わせながら設置し、ボルトで固定します。
以降は1段分ずつ掘削と同時にライナープレートを設置していきます。必要に応じて腹起し材や切梁材も設置しながら、所定の深さまで掘り進めます。床付け(最終掘削面の仕上げ)は人力で行い、過掘りしないよう注意します。
立坑の深さや地盤条件に応じて、山留支保工(切梁・腹起し)を設置します。支保工の仕様は応力計算に基づいて決定します。
縦梁を設置できる深さまで掘削したら、縦梁を設置し、ブラケットを腹起し設置位置に溶接して固定します。ブラケット設置後、ラフテレーンクレーンを使用して腹起しと切梁を設置します。
腹起しと切梁はボルトでしっかりと固定し、ジャッキの設置位置は同一方向に偏らないよう交互に配置します。これにより、土圧を均等に受け止め、立坑の安定性を確保します。
立坑底部の基礎として、砕石(C-80)を油圧クラムシェルなどで投入します。投入後は人力で所定の幅と厚さになるよう敷き均し、タンピングランマやプレートコンパクタを使用して十分に締め固めます。
基礎材の均一な敷設と適切な締固めは、立坑底部の安定性を確保するために重要です。特に湧水がある場合は、排水処理を行いながら作業を進めます。
立坑底部の基礎コンクリートを打設します。コンクリートの打設は、ラフテレーンクレーンにコンクリートホッパを取り付け、吐出口と打込み面の高さが1.5m以下になるよう調整して行います。または、コンクリートポンプ車を使用して打設する方法もあります。
コンクリートは練混ぜ完了から打設完了までの時間を1.5時間以内に収め、納品伝票の出荷時間と打設完了時間で管理します。一区画のコンクリートは連続して打設し、表面が水平になるよう施工します。
コンクリートの締固めには高周波バイブレーターを使用し、コンクリートが隅々まで行き渡るようにします。ただし、バイブレーターによる横流しが生じないよう注意が必要です。
コンクリート打設後は適切な養生を行います。打設終了後、コンクリート表面を保水性のある養生マットで覆い、所定の養生期間中は散水を適宜行って湿潤状態を保ちます。
低温や急激な温度変化、乾燥、衝撃などからコンクリートを保護し、一日の平均気温が4℃以下になると予想される場合は防寒養生も実施します。適切な養生によってコンクリートの強度発現を促進し、ひび割れを防止します。
立坑としての役割が終了したら、山留支保工(切梁・腹起し)の撤去と埋戻しを行います。支保工材の撤去は埋戻し作業と並行して行い、所定の位置まで埋め戻した後、ラフテレーンクレーンで撤去します。
ライナープレートは1段ずつ取り外しながら埋戻しを進めます。埋戻し材料はバックホウや油圧クラムシェルで投入し、掘削土や流用土の中から埋戻しに適した良質の土砂を選定します。埋戻し前に埋戻し箇所の雨水や雑物を除去することも重要です。
埋戻しの転圧は、一層の厚さが30cmを超えない範囲で振動ローラやタンピングランマを使用して入念に締め固めます。不等沈下が生じないよう丁寧に転圧することで、地盤の安定を確保します。
鋼矢板工法は、地中に鋼矢板を打ち込んで土留め壁を構築し、内部を掘削して立坑を形成する工法です。地下水位が高い場所や軟弱地盤でも適用でき、中~大規模の立坑に適しています。鋼矢板の遮水性を活かした止水効果も期待できます。
立坑築造の最初のステップは、鋼矢板の搬入です。一般的にⅡ型(厚さ約10.5mm、幅400mm)などの鋼矢板をトレーラーで現場に運び込みます。搬入時には過積載にならないよう、運搬車の性能や規格を考慮します。
安全確保のため、資材の搬入・搬出時には誘導員を配置します。鋼矢板はラフテレーンクレーンを使用して、あらかじめ設置した作業ヤードに荷降ろしします。
鋼矢板の打込み作業では、ラフテレーンクレーンとバイブロハンマーを組み合わせて使用します。まず、打込み箇所に施工ラインを設定し、床均しを行って鋼矢板打込み定規が設置できるようにします。
クレーンの親ワイヤーにバイブロハンマーを装着します。この際、すべての機器が正常に作動することを確認し、安全な作業環境を整えます。
補助ワイヤーロープで鋼矢板を吊り上げ、バイブロハンマーのチャックでつかみます。鋼矢板を所定の位置に垂直に立て込み、バイブロハンマーを起動して打ち込みます。
作業中の安全確保のため、バイブロハンマー作動時も鋼矢板を吊った補助ワイヤーロープは緩める程度にしておきます。バイブロハンマーの重量で鋼矢板に曲がりや亀裂が発生しないよう、バイブロハンマーの重量を鋼矢板に全て預けないように注意します。
鋼矢板は、互いにインターロック(継手)をかみ合わせながら連続して打ち込み、閉じた矩形や円形の土留め壁を形成します。この際、鋼矢板の傾きや打ち込み深さを常に確認し、精度を保ちながら作業を進めます。
鋼矢板の打込みが完了したら、立坑内部の掘削を開始します。掘削深さが5m程度までは通常のバックホウを使用し、それ以上の深さでは油圧クラムシェルなどの専用機械を使用します。
掘削した土砂はダンプトラックに積み込み、指定の仮置場に運搬します。作業中の安全確保のため、開口部周辺に単管パイプなどで手すりを設置します。
掘削は段階的に行い、各段階での掘り下げ位置は支保工設置位置の下段より1.0m下がりで施工します。掘削時には湧水や土質の変化に注意し、床掘りは偏りなく平均して掘り下げます。最終的な床付け(掘削底面の仕上げ)は人力で行い、過掘りしないよう注意します。
立坑の深さや地盤条件に応じて、山留支保工(切梁・腹起し)を設置します。支保工の仕様は応力計算に基づいて決定します。
掘削が支保工設置位置の下段より1.0m下がったら、鋼矢板にブラケットを腹起し設置位置に溶接して固定します。ブラケット設置後、ラフテレーンクレーンを使用して腹起しと切梁を設置します。
腹起しと切梁はボルトでしっかりと固定し、ジャッキの設置位置は同一方向に偏らないよう交互に配置します。これにより、土圧を均等に受け止め、立坑の安定性を確保します。
掘削が完了し床付けが終わったら、立坑底部の基礎材として砕石(C-80)を油圧クラムシェルなどで投入します。投入後は人力で所定の幅と厚さになるよう敷き均し、タンピングランマやプレートコンパクタを使用して十分に締め固めます。
基礎材の均一な敷設と適切な締固めは、立坑底部の安定性を確保するために重要です。特に湧水がある場合は、排水処理を行いながら作業を進めます。
立坑底部の基礎コンクリートを打設します。コンクリートの打設は、ラフテレーンクレーンにコンクリートホッパを取り付け、吐出口と打込み面の高さが1.5m以下になるよう調整して行います。または、コンクリートポンプ車を使用して打設する方法もあります。
コンクリートは練混ぜ完了から打設完了までの時間を1.5時間以内に収め、納品伝票の出荷時間と打設完了時間で管理します。一区画のコンクリートは連続して打設し、表面が水平になるよう施工します。
コンクリートの締固めには高周波バイブレーターを使用し、コンクリートが隅々まで行き渡るようにします。ただし、バイブレーターによる横流しが生じないよう注意が必要です。
コンクリート打設後は適切な養生を行います。打設終了後、コンクリート表面を保水性のある養生マットで覆い、所定の養生期間中は散水を適宜行って湿潤状態を保ちます。
低温や急激な温度変化、乾燥、衝撃などからコンクリートを保護し、一日の平均気温が4℃以下になると予想される場合は防寒養生も実施します。適切な養生によってコンクリートの強度発現を促進し、ひび割れを防止します。
立坑としての役割が終了したら、山留支保工(切梁・腹起し)の撤去と埋戻しを行います。支保工材の撤去は埋戻し作業と並行して行い、所定の位置まで埋め戻した後、ラフテレーンクレーンで撤去します。
埋戻し材料はバックホウや油圧クラムシェルで投入し、掘削土や流用土の中から埋戻しに適した良質の土砂を選定します。埋戻し前に埋戻し箇所の雨水や雑物を除去することも重要です。
埋戻しの転圧は、一層の厚さが30cmを超えない範囲で振動ローラやタンピングランマを使用して入念に締め固めます。不等沈下が生じないよう丁寧に転圧することで、地盤の安定を確保します。
埋戻しが完了したら、油圧式杭圧入引抜機を設置して鋼矢板の引抜きを行います。引抜き作業は打ち込み時と同様に油圧式杭圧入引抜機で行い、鋼矢板の吊り込みはラフテレーンクレーンを使用します。
鋼矢板の引抜き後には空洞が生じるため、砂などで確実に充填して地盤沈下を防止します。空隙による地盤沈下の影響が大きいと判断される場合は、監督者と協議して対策を講じます。特に推進管上の鋼矢板を引き抜く際は、管に影響を与えないよう細心の注意を払います。
鋼矢板圧入工法は、油圧式杭圧入引抜機を使用して鋼矢板を地中に静かに押し込む工法です。振動や騒音が少なく、周辺環境への影響を最小限に抑えられるため、市街地での施工に適しています。地下水位が高い場所や軟弱地盤でも適用でき、鋼矢板の遮水性を活かした止水効果も期待できます。
立坑築造の最初のステップは、鋼矢板の搬入です。一般的にⅡ型(厚さ約10.5mm、幅400mm、長さ8m程度)などの鋼矢板をトレーラーで現場に運び込みます。搬入時には過積載にならないよう、運搬車の性能や規格を十分に考慮します。
安全確保のため、資材の搬入・搬出時には誘導員を配置します。鋼矢板はラフテレーンクレーンを使用して、あらかじめ設置した作業ヤードに荷降ろしします。
鋼矢板の打込みには油圧式杭圧入引抜機を使用します。まず、鋼矢板圧入のための基準となる法線(施工ライン)を設定します。この法線に沿って、反力架台を水平に設置し、油圧式杭圧入引抜機と反力ウェイトを据え付けます。
油圧式杭圧入引抜機は、反力を得るために既に打ち込まれた鋼矢板やウェイトを利用して新たな鋼矢板を押し込む機械です。精度の高い施工を実現するため、機械の据付けは慎重に行います。
油圧式杭圧入引抜機のチャックに1枚目の鋼矢板(№1)を建て込み、法線との位置関係や垂直度を確認した後、圧入を開始します。№1鋼矢板を所定の高さまで圧入したら、次に2枚目(№2)の鋼矢板を途中まで圧入します。
油圧式杭圧入引抜機が安全に自走できる位置まで№2鋼矢板を圧入した後、機械を自走させて№2鋼矢板を所定の高さまで圧入します。このように、反力架台を用いて4~5枚程度の鋼矢板を圧入した後、反力架台を撤去します。
所定の鋼矢板の圧入後、油圧式杭圧入引抜機を反転させて反力矢板を引き抜き、その位置に正規の鋼矢板を建て込んで圧入します。このようにして、計画した四角形や円形などの立坑の形状に沿って鋼矢板を順次圧入していきます。
鋼矢板圧入工法の特徴は、振動や騒音が少なく、周辺地盤への影響が小さいことです。油圧の力で静かに鋼矢板を押し込むため、地盤の緩みが少なく、高精度な施工が可能になります。
鋼矢板の圧入が完了したら、立坑内部の掘削を開始します。掘削深さが5m程度までは通常のバックホウを使用し、それ以上の深さでは油圧クラムシェルなどの専用機械を使用します。
掘削した土砂はダンプトラックに積み込み、指定の仮置場に運搬します。作業中の安全確保のため、開口部周辺に単管パイプなどで手すりを設置します。
掘削は段階的に行い、各段階での掘り下げ位置は支保工設置位置の下段より1.0m下がりで施工します。掘削時には湧水や土質の変化に注意し、床掘りは偏りなく平均して掘り下げます。最終的な床付け(掘削底面の仕上げ)は人力で行い、過掘りしないよう注意します。
立坑の深さや地盤条件に応じて、山留支保工(切梁・腹起し)を設置します。支保工の仕様は応力計算に基づいて決定します。
掘削が支保工設置位置の下段より1.0m下がったら、鋼矢板にブラケットを腹起し設置位置に溶接して固定します。ブラケット設置後、ラフテレーンクレーンを使用して腹起しと切梁を設置します。
腹起しと切梁はボルトでしっかりと固定し、ジャッキの設置位置は同一方向に偏らないよう交互に配置します。これにより、土圧を均等に受け止め、立坑の安定性を確保します。
掘削が完了し床付けが終わったら、立坑底部の基礎材として砕石(C-80)を油圧クラムシェルなどで投入します。投入後は人力で所定の幅と厚さになるよう敷き均し、タンピングランマやプレートコンパクタを使用して十分に締め固めます。
基礎材の均一な敷設と適切な締固めは、立坑底部の安定性を確保するために重要です。特に湧水がある場合は、排水処理を行いながら作業を進めます。
立坑底部の基礎コンクリートを打設します。コンクリートの打設は、ラフテレーンクレーンにコンクリートホッパを取り付け、吐出口と打込み面の高さが1.5m以下になるよう調整して行います。または、コンクリートポンプ車を使用して打設する方法もあります。
コンクリートは練混ぜ完了から打設完了までの時間を1.5時間以内に収め、納品伝票の出荷時間と打設完了時間で管理します。一区画のコンクリートは連続して打設し、表面が水平になるよう施工します。
コンクリートの締固めには高周波バイブレーターを使用し、コンクリートが隅々まで行き渡るようにします。ただし、バイブレーターによる横流しが生じないよう注意が必要です。
コンクリート打設後は適切な養生を行います。打設終了後、コンクリート表面を保水性のある養生マットで覆い、所定の養生期間中は散水を適宜行って湿潤状態を保ちます。
低温や急激な温度変化、乾燥、衝撃などからコンクリートを保護し、一日の平均気温が4℃以下になると予想される場合は防寒養生も実施します。適切な養生によってコンクリートの強度発現を促進し、ひび割れを防止します。
立坑としての役割が終了したら、山留支保工(切梁・腹起し)の撤去と埋戻しを行います。支保工材の撤去は埋戻し作業と並行して行い、所定の位置まで埋め戻した後、ラフテレーンクレーンで撤去します。
埋戻し材料はバックホウや油圧クラムシェルで投入し、掘削土や流用土の中から埋戻しに適した良質の土砂を選定します。埋戻し前に埋戻し箇所の雨水や雑物を除去することも重要です。
埋戻しの転圧は、一層の厚さが30cmを超えない範囲で振動ローラやタンピングランマを使用して入念に締め固めます。不等沈下が生じないよう丁寧に転圧することで、地盤の安定を確保します。
埋戻しが完了したら、油圧式杭圧入引抜機を設置して鋼矢板の引抜きを行います。引抜き作業は打ち込み時と同様に油圧式杭圧入引抜機で行い、鋼矢板の吊り込みはラフテレーンクレーンを使用します。
鋼矢板の引抜き後には空洞が生じるため、砂などで確実に充填して地盤沈下を防止します。空隙による地盤沈下の影響が大きいと判断される場合は、監督者と協議して対策を講じます。特に推進管上の鋼矢板を引き抜く際は、管に影響を与えないよう細心の注意を払います。
【お役立ち情報】
コメント
コメント一覧 (3件)
This post will help the internet users for setting up new web site or even a weblog from start to end.
Greetings from Florida! I’m bored to tears at work so I decided to check out your website on my iphone during lunch break.
I really like the knowledge you provide here and can’t wait to take a
look when I get home. I’m amazed at how fast your blog loaded on my cell phone ..
I’m not even using WIFI, just 3G .. Anyhow,
good blog!
I used to be abhle to find good ijfo from your log posts.
Feell free to surf to my homepage – Anita